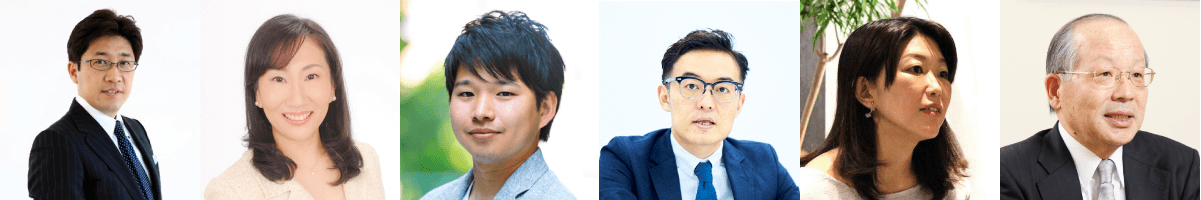忙しさにかまけてカレンダーをめくり忘れたまま新しい月を迎えるように、自分だけを置き去りにして、世間がどんどん先に進んでいると感じることはないだろうか。僕は「働き方改革」を巡る議論から、それに似た感覚を覚えることがある。
かつて僕は会社員だった。2017年の今、会社員を続けていたとして、自分自身が長時間労働を抑制するために能動的に動けていたかは甚だ疑問だ。「サラリーマンは副業に挑むべし」といった記事があっても、副業禁止の会社に身を置いていることを理由に、どこか冷ややかな目で見ていたかもしれない。
とはいえ、フリーランスのライターとして活動している今は、そうした感覚が徐々に薄れつつあるのも事実。「キャリア」や「働き方」を主なテーマに据えてさまざまな記事を書きながら、世の中のカレンダーが確実に進んでいることを知り、自分も何とかそこに同期できていると感じるのだ。まだまだ経験は浅いものの、フリーランス・ライターとしての日々の仕事は少しずつ僕の認識を変えている。そんな体験談を書くにあたり、まずは僕が「何をしているフリーランスなのか」を説明したい。
「ライター」を名乗る人の数だけ、独自のスタイルがある
一口にフリーランスといっても、そこにはいろいろな職種がある。ライターやデザイナー、エンジニア。イラストレーターにカメラマン(男女)。セールスやマーケティング、人事、広報などのビジネス分野でプロフェッショナルとして独立している人もいるし、複数の店舗で場所を借りながら活動する美容師もいる。建設現場などで活躍する職人にも個人事業主、つまりは個人で勝負するフリーランスとして活動している人が多い。
僕の社会人キャリアのスタートは2004年。それから2014年までの10年間は求人広告の営業をしていた。当時は「一人親方」と呼ばれるフリーランス職人のもとへよく足を運んだ。たいていは自宅兼事務所が商談場所だったが、中には20代半ばにして高級住宅街に立派な戸建てを構えている人もいた。「現状のままでは仕事を受けきれないから」と、初めて人材募集を行うケースも。今にして思えば、一匹狼のフリーランスが組織作りを始めようとする貴重な機会に立ち会っていたのだった。
日本社会において、フリーランスという働き方は決して目新しいものではない。業界によっては「元請けから外注先へ」という確かな仕事の流れが古くから存在し、そうした業務の受け皿としてフリーランスが機能してきた。
ライターという職種も、歴史あるフリーランス職種の一つだ。ただ、その定義はかなり複雑になってきている。同業者と話していても、ライターと名乗って活動する人の数だけ独自の仕事のスタイルが存在するように感じるのだ。特定の食のジャンルを追求してコメンテーターとして活躍する人、とある音楽誌のためだけに長年寄稿を続けている人、ウェブマーケティングの専門家としてライティング技術を使いこなす人……。皆、名刺にライターと刷っているが、その主戦場はバラバラ。多くの場合、その違いはライターとなるまでの経緯や経験によるものだ。
「カメラマン」に(男女)を付けてしまう癖が抜けない
僕自身がライターとして抱える案件の種類も、特殊といえば特殊だと思う。売上の約半分をこの『Business Nomad Journal』のようなオウンドメディアやニュースサイトに掲載される記事の執筆で、もう半分を業界大手が展開するポータルサイト内の求人広告制作で得ている。知り合いの同業者の中で、どちらかだけをやっている人は大勢いるが、両方を同じくらいやっている人はほとんどいない。
お気づきだろうか? 僕はこの稿の冒頭あたりで「カメラマン(男女)」という妙な表現を使った。「マン」なのに「男女」。この表現に違和感を覚えず、さらりと読み飛ばした人は、求人広告を扱う業務に携わってきた経験者だろう。
多くの求人広告メディアでは、「(男女)」を付けずに「カメラマン」とだけ表記することは厳禁。カメラマンという職種名は一般的に広く使われているが、募集・採用における男女差別を禁じた男女雇用機会均等法を遵守する観点から、男性のみを対象としているようにとらえられる「カメラマン」のみでの使用を不可としている。「カメラマン(男女)」なら可。うまく言い換える方法を考えてみても、今ひとつ定義が曖昧な「フォトグラファー」「写真家」では仕事内容に誤解を招く恐れがあり、「カメラパーソン」では何の募集なのか伝わりづらい。「撮影スタッフ」だと少しプロっぽさが足りないかも……。そんなわけで、求人広告では今も「カメラマン(男女)」という冗談のような、しかしながら絶対に必要な表現が使われているのだ。
体に染み付いた癖はなかなか抜けない。僕は10年間求人広告だけを扱い、今でも制作に携わっているので、このコラムのように求人広告ではない記事を書いているときもつい「カメラマン(男女)」と書いてしまうことがある(先ほどの表記はわざとだとしても)。そんな理由でせっせと原稿を直しているライターは、おそらくほとんどいないだろう。
好きなことをやり、新たな知見を得て活用する
なぜ、オウンドメディアなどでの執筆と求人広告制作を並行させているのか。フリーランスになったばかりの頃は、経験を生かせる仕事を交えて生計を立てていくことが目的だった。
10代の頃からぼんやりと考え続けていた「物書きになりたい」という思いを遂げるため、求人広告代理店から編集プロダクションに転職。「既婚者・子あり」というステータスながら、31歳にして未経験でライター業に挑戦した。そしてその半年後にはフリーランスになるという、我ながら無茶だとしか思えない道を歩んでしまっていた。まずは、どう暮らしていくかを考えるほかなかったのだ。
編集プロダクションでの学びはとても濃密で、編集者・ライターとしての豊富な実績を持つ先輩から、今につながる多くのことを教わった。とはいえ、たった半年でその環境を飛び出してしまった身。ライター名を出して掲載してもらえるような記事を書くには実績が不足していた。ライティングの基礎知識を生かして少しずつクライアントを増やし、求人広告の専門知識を生かして基盤となる売上を作るという日々だった。明らかに準備不足の状態でフリーランスになったため、当初はそれ相応の苦しみも経験した(詳細は次回の稿で告白したい)。
やがてクライアントに恵まれ、オウンドメディアなどでの執筆と求人広告制作という二本柱が形になっていく中で、僕は2つのことに気づいた。1つは、自分のファーストキャリアである求人広告の仕事が「今でも好き」だということ。抜群に優れた集客力を誇るポータルサイトを使っても、ただ掲載するだけで狙い通りの人材に応募してもらえるような企業はごくわずかだ。採用市場の動向を踏まえて企業の魅力を見極め、取材したり資料を精査したりしながらそれを裏付けられるプロの広告制作者がいなければ、採用は成功しない。この過程に今も携われることが純粋にうれしい。
もう1つは、二本柱の仕事を行き来する中で「常に新しい知見を得て活用できる」ということだ。オウンドメディアなどの仕事で企業取材やインタビューを繰り返し、世の中のトレンドや働く個人の思いを知ることで、日々新しい知見をインプットできる。その状態で求人広告制作の現場へ行けば、企業の魅力を誰に届けるべきか、どのような言葉で表現すべきかといった新しいアウトプットが浮かんでくる。逆も然り。多種多様な業界に出切りする求人広告制作の現場で見聞きしたことが、インタビューの切り口として生きることも多いのだ。
今ではこのサイクルを回していくことこそ、僕が二本柱で仕事をする意味となった。好きなことをやる。それを繰り返すことで常に新しい知見を得て活用できる。言葉にして振り返るのは簡単だが、もしフリーランスになっていなければ、このサイクルを実感することは難しかったと思う。
ライター:多田 慎介
フリーランス・ライター。1983年、石川県金沢市生まれ。大学中退後に求人広告代理店へアルバイトとして入社し、転職サイトなどを扱う法人営業職や営業マネジャー職に従事。編集プロダクション勤務を経て、2015年よりフリーランスとして活動。個人の働き方やキャリア形成、企業の採用コンテンツ、マーケティング手法などをテーマに取材・執筆を重ねている。