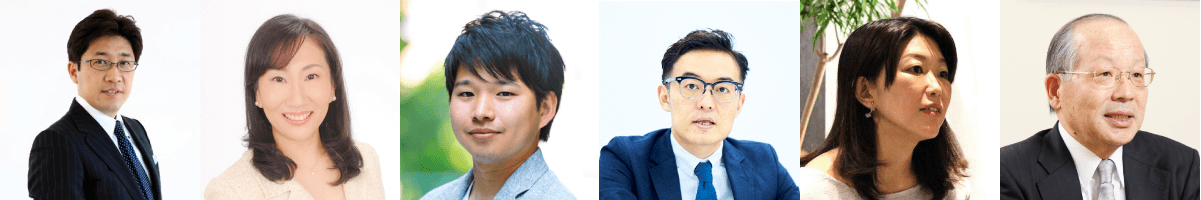僕は今、ライターという仕事で生計を立てている。まったく計画性のない20代を経て、この仕事にたどり着いている。
「将来は物書きになりたい」と考え始めたのは18歳の頃だった。そして実際に「物書き」を意味する、ライターという肩書きを名刺に刷るようになったのは31歳のとき。思えば実に長い期間、夢の職業は夢でしかなく、現実とはかけ離れた場所にあったのだった。
物書きという曖昧な言い方だと、少し伝わりづらいかもしれない。この言い方は僕が社会人になってから、周囲の人々に対して、ごく控えめに夢を語るために使っていたものだ。18歳の頃から夢見ていた職業を正しく言うなら、それは「小説家」だった。当時の僕がイメージしていた小説家の仕事といえば、誰にも邪魔されることのない自分だけの空間にこもり、己の頭の中から湧き上がる創作の世界を舞台にした物語を書き連ねるというもの。
しかし現実には、「小説家を目指している」と人に語るのは気が引けてしまう自分がいた。僕は20歳からスーツにネクタイを身にまとい、飛び込み訪問が主体の泥臭い営業の仕事をしていた。静かな書斎で自分と向き合う小説家に比べれば、まるで正反対の世界だ。夢を聞かれれば、どことなく濁して「物書き」と答えるのが精いっぱいだった。
しかし11年後、僕はそうした泥臭い経験の数々を生かす形でライターとなった。これもまた小説家とは異質な世界だが、広い意味での物書きには違いない。想像以上にアクティブで、かつての営業のように泥臭い仕事だけれど。
同世代の芥川賞作家の小説が、まったく面白くなかった
僕が求人広告代理店での営業職という仕事を選んだのは、主に2つの理由からだった。1つは物書き仕事がしたいと思って応募した編集プロダクションの書類選考にまったく通らなかったため、少しでも近しい領域で働きたいと思ったこと。そしてもう1つは、当時「芥川賞最年少受賞」として話題になっていたある同年代の若手作家の小説を、まったく面白いと思えなかったことだった。
「若者の瑞々しい感性」や「現代の言葉・表現」でつづられた小説に登場するのは、今を生きる僕と同世代の人物。実に生意気な考えなのだが、そんな彼らの生き様やストーリーに、僕は何も心を惹かれなかったのだった。所詮は社会経験のない「子ども」が描いた作品で、そこには実社会で生きる人間の本質的な姿が何も描かれていない……。そんな感想を抱いた。単純に、同世代の才能ある作家に対する妬みもあったのだと思う。自分はまだ何者でもないのに。
そのときに感じたのは、小説を本気で書きたいと思うなら、社会経験を積まなければいけないということだった。何だかジブリ映画のヒット作の一節のようだが、本当にそう思ったのだ。だから僕は、とりあえずスーツにネクタイを締める仕事をするべきだと考えた。そうして世の中を学び、人というものを知るべきだと。
今、振り返ってみて思う。20歳の自分は、考え方は中学生のように稚拙であったけれど、判断としては間違えていなかった。
書き手ではなく、法人営業の経験を買ってもらった
フリーペーパーやインターネットをプラットフォームにして求人メディアが進化を続けていた2000年代、僕はその営業職としてキャリアを積んだ。広告枠を売ることだけが仕事ではなかった。クライアント企業の経営者や人事担当者にインタビューし、それを広告表現に反映するための企画出しも求められた。
グラフィックデザインはまったくできないけれど、コピーを考えることはできる。ときには広告制作の仕事をすべて自分で抱え、納得のいくまで職人的に作り込むこともあった。営業としては非常に生産性の低いあり方だったが、そうしてこだわりに抜いた結果、絶大な信頼を寄せてくれるクライアントを得た。営業チームのマネジメントという貴重な経験もさせてもらった。
そんな風に過ごしていた31歳のときに、とある編集プロダクションの求人に出会ったのだった。仕事はライター・編集者。30代の未経験者にはほとんど門戸が開かれていない職種だと思っていたが、その会社は書き手としての経験ではなく、法人営業としての社会人経験を買ってくれたのだった。
そうして、遠い夢として、もはや夢のまま薄れていくものだと思っていた「物書きになりたい」という思いが実現した。
ときどきの経験は、何一つ無駄にならないと思う
ライターの世界で活躍している人は、実に多種多様な経験を持っている。僕のように企業勤めでまったく異なる職種のキャリアを積んできた人も多い。異分野の経験は、そのままライターとしての強みにつながる。
僕がずっと人材・キャリアの世界に興味を持ち、今もそうした案件をメインとしているように。
20歳の僕は、とりあえずスーツにネクタイを締めて仕事をしようと思った。稚拙だったけれど、その判断のおかげで僕はライターになれた。偶然の積み重ねと言ってしまえばそれまでだが、現在の仕事につながる必然性も確かにあったのだ。
人生は変わっていくし、ときどきの経験は何一つ無駄にならない。そんな哲学を得て、僕は今のフリーランス生活を楽しんでいる。やがてはこの経験が、まったく違う仕事に就く助けになるのではないかとも思う。やがて、また本気で小説を書きたいと思ったときには、出来栄えは別として、書くネタにはまったく困らない自分がいるだろう。
ライター:多田 慎介
フリーランス・ライター。1983年、石川県金沢市生まれ。大学中退後に求人広告代理店へアルバイトとして入社し、転職サイトなどを扱う法人営業職や営業マネジャー職に従事。編集プロダクション勤務を経て、2015年よりフリーランスとして活動。個人の働き方やキャリア形成、企業の採用コンテンツ、マーケティング手法などをテーマに取材・執筆を重ねている。