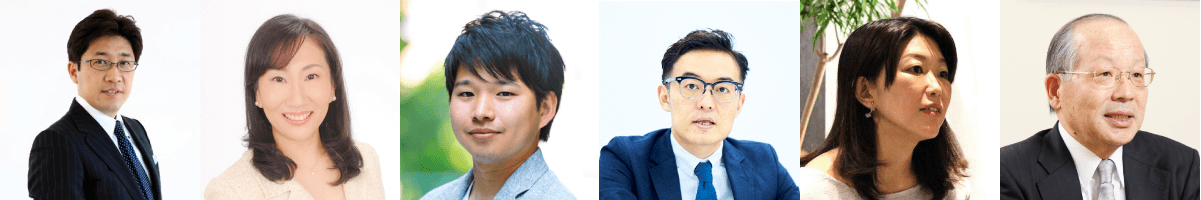今回お話をうかがうのは、早稲田大学政治経済学術院教授、同大学トランスナショナルHRM研究所所長の白木 三秀さん。国士舘大学政経学部助教授、同教授を経て、99年から現職へ。社会政策、人的資源管理を専門とし、多国籍企業が複数の国籍かつ文化的背景の従業員を組織し、経営資源として活用する「国際人的資源管理」を日本に広めた第一人者です。
海外での現地マネジメントの実状や、グローバルな働き方の今後についてお話を伺いました。前編では、アジアを研究対象に選んだ理由について、学生時代から遡ってお聞きしました。
※本インタビューは、フライヤー×サーキュレーションの「知見と経験の循環」企画第14弾です。経営者や有識者の方々がどのような「本」、どのような「人物」から影響を受けたのか「書籍」や「人」を介した知見・経験の循環について伺っていきます。
見向きもされなかったアジアを研究対象に。貫いたのは徹底的な「現場主義」
Q:白木さんは、どのような経緯で今の研究分野を決められたのでしょうか。
白木 三秀さん(以下、白木):
私が大学に入った1970年代前半は、大学紛争まっただ中。授業は休講が多く、試験もありませんでした。ですが、教員にとってはそんなことは関係ないので、フランス語の授業は数回しか受けていないにもかかわらず、ルソーの『社会契約論』を原書で読んでレポートにまとめないといけないような、無茶な状況でした(笑)。
日本でモラトリアムを続けているだけではなく、せっかくなら海外を見てみようと思い、1年間休学してヨーロッパを旅しました。ですが、訪れたロンドンは、オイルショックの余波で不況に陥り、ストライキが頻発していた。結局、日本だろうがイギリスだろうが、不満を持っている人がたくさんいたわけです。そこで「国内外がこんなに荒れているのはなぜなのか?」という疑問を探りたいという思いから、大学院に進学し、日本の労働市場を中心に労働関係の分野を研究することに決めました。当時は今就職するよりも、もう少し研究を深めてみようというくらいの気持ちでした。
海外に注目するようになったのは大学講師になった頃のことです。研究を進めるなかで、「日本の労働環境だけを見ていても、労働市場の実態を正しく知ることはできない」と気づきました。
Q:日本だけを見ていてはダメだと。それはなぜでしょうか。
白木:
ちょうど1970年代後半からNIES(新興工業経済地域)が急成長を始めており、日本企業は円高の影響で台湾や東南アジアをはじめ、海外へ軒並み進出するようになったからです。1985年のプラザ合意で円高が加速し、海外直接投資が急増した時期だった。
東大の教授をされていた隅谷三喜男先生がすでに、韓国の労働市場を研究されていたことに影響を受け、「韓国は先例があるから、未知の領域が多い台湾について研究しよう」と思い、修士論文では「台湾の労働市場」をテーマにしました。
博士の学生になったとき、ある先生から「文献や統計データだけで論文を書いていちゃまずいぞ。アジアを直接見に行ってこい」と薦められ、縁あってタイ、マレーシアをはじめ、韓国や台湾、東南アジアを短期間まわりました。この頃から研究したいテーマが労働市場から雇用の問題、そして雇用問題の解決に不可欠な雇用管理や人材育成を扱う、人的資源管理へと移っていきました。
当時の私は生意気なことに、ヨーロッパやアメリカといった先進国を研究の主軸には置かないというポリシーを持っていました。社会科学の王道は「欧米の知見から学ぶ」というもので、東アジア、東南アジアを研究対象に選ぶ研究者はほとんどいない時代でした。アジアを研究すると言うと、「(大学の)就職は大丈夫か」と周囲から心配される始末。
Q:今なら研究するうえで非常にホットな地域だと思うのですが、そんな時代だったのですね!
白木:
そうですね。シンガポールを例にとると、今や日本よりも国民一人当たりのGDP(国内総生産)が高く、経済的に豊かな国の一つとなっていますが、1980年代はシンガポールですら中進国だったのです。日本はアジアにおける圧倒的な先進国であり、日本には東南アジアの国々から学ぶという発想は皆無に等しかった。とはいえ、日本はアジアの一角を占めていることに変わりはありません。それなのに、アジアについて研究している日本人がほとんどいないのは由々しき事態だと思ったのです。そこで、日本を拠点にしながらも自分の足でアジアの最前線に出向き、現場主義を追求しながら、世界に通用する研究者になりたいという思いが芽生えました。
Q:現場主義を追求したいと思っておられたのですね。
白木:
ここまで現場にこだわるようになったのには、理由があります。それは、終戦直後の日本の社会科学者たちが、「日本は衰退する」という悲観的な予測に終始し、その後訪れる高度経済成長期を予想できなかったからです。彼らは復興時の製造業などが目覚ましく発展していこうとする現場を見ていなかったからなんです。日本や他のアジアの国々の現場に出向いて、生のデータを得ることなしに研究はできないと考えていました。この研究スタンスを、パスカルの「人間は考える葦である」という格言をもじって、「人間は考える『足』である」と、私が最初に書いた本の序文にも書いています。このスタンスは今も変わっていませんね。
本の要約サイト フライヤーのインタビューはこちらから!
海外トレーニー制度の効果を高めるための秘訣や、
グローバル教養を身につけるうえでの、
おすすめの本について白木先生にお聞きしました。
内向き志向と言われがちな若手社員が、グローバル人材へと成長するためには、
どんなスキルや経験が必要なのでしょうか?

専門家と1時間相談できるサービスOpen Researchを介して、企業の課題を手軽に解決します。業界リサーチから経営相談、新規事業のブレストまで幅広い形の事例を情報発信していきます。