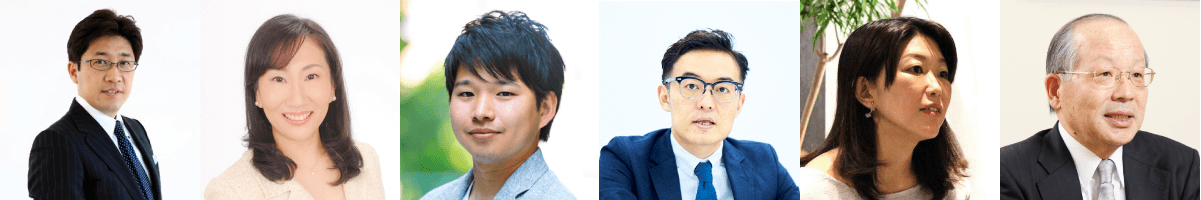経営危機という言葉は、決して珍しいものではありません。程度に差はあっても、経営危機に瀕したことがない企業のほうが少数派かもしれないのです。
しかし、経営危機にどのような対策を採ったか、またそもそも経営危機に陥らないためにどうするかということについては、様々な意見が交わされつつもいまだ「正解」が導きだされていないように思えます。
その答えは会社の数だけあるのかもしれません。そこで今回は、複数の会社で経営にたずさわり、経営危機に直面してきた経験を持つ、深尾愛二郞氏に話を伺いたいと思います。
もともと理系に興味があったが、物理が苦手になり文系の道へ。
そして、就職では、ユニークな製薬企業と出会う。
Q:深尾さんは、東洋醸造、そして吸収合併されたり旭化成を経て、製紙卸企業、アルプス技研など、様々な企業を経験されています。最初は、東洋醸造に入社して経理を担当されていたと聞いています。
深尾愛二郞氏(以下、深尾):
もともと子どもの頃は、科学に興味があり、理系に進みたいと思っていたのです。ところが、勉強をサボっていたら物理がダメになり、自然と理系への進学を諦めざるを得なくなってしまった。そこで、将来、実業界でビジネスをするなら、経済を学んだ方がいいだろうと考えて、経済学部に進んだんです。
当時、大学3年の終わりには就職活動が始まったのですが、購読していた経済誌に、たまたま東洋醸造が紹介されていたんです。医家向けの薬、動物薬が中心で、一般的な知名度は高くないが、ユニークな会社だと感じました。合成ペニシリンを日本で始めて開発したり、いまも骨粗しょう症薬として広く使用されているエルシトニン、移植手術で使われる免疫抑制剤のプレディニンの開発など、業界では相当に有名な企業だったんです。
Q:大学進学時には理系を諦めていたそうですが、心の中にはそういった理系企業への興味が息づいていたのですね。
深尾:
大学時代も経済誌だけでなく、「自然」「科学朝日」といった科学誌を講読していました。大学内では、三大学ゼミといって複数の大学をまとめてゼミ発表をするようなイベントも企画運営していたのですが、なぜか、「商社向きじゃない」と大学の就職課からは指摘されました。
Q:東洋醸造、後に旭化成に吸収されますが、そこでは長い間、経理部門にいらっしゃったと聞いています。ところが、その後一転して、海外担当になられていますがこれはどういった経緯だったのでしょうか?
深尾:
経理は入社してすぐに配属されてから、20年もやっていました。本音を言えば、経理はやりたくなかったんです。それを20年も続けたのですから、まったく嫌というわけでは無かったんですよ。すると「いつまでも経理ばかりやっていると、偏った人間になるぞ」と社長に言われたんです。そう言われてすぐに異動になり、海外マーケット担当になりました。日本で販売しているエルシトニンやプレディニンをヨーロッパやアメリカでも承認を取って販売していこうというプロジェクトだったんです。
ところが、医薬品で海外進出しようとすると、世界のトップ企業とやりあうことになります。すると、スミスクラインビーチャム(現:グラクソ・スミスクライン株式会社)、バイエルといった世界のトップ企業から声がかかるんです。企業規模から言うと比較にならないほどの差があるにもかかわらず、提携の話だったり、もっと突っこんで言うとM&Aの話が舞いこんでくる。
というのも、当時の医薬品業界では、新薬の開発が高コストでリスクが高いという理由で行き詰まっていた。そこで、いくつもの企業で共同開発することでリスク分散を図るという動きが増えていたんです。これは海外市場だけの動きではありませんでした。実のところ、後に旭化成が東洋醸造を吸収合併したのも、東洋醸造が持つ開発力に注目したからなんです。
長い経理の仕事を経て、海外プロジェクト担当に
そこで見た、成功するM&Aと失敗するM&A
Q:海外の医薬品マーケット、ましてM&Aの話が飛びかうような環境ですと、それまでの仕事とは勝手が違うことも多かったと思います。一方で、なかなかそういう環境で仕事をするチャンスも少ないのではないでしょうか。深尾さんご自身は、そこでどんなことを学ばれたと思っておられますか?
深尾:
実際、多くのM&A事例を見ましたが、うまくいかないケースも多いのです。M&Aでは、どんなに優れた商品、開発力を持つ企業を買収したとしても、それを自社でコントロールして拡大させることができるのかという視点が必要です。これは医薬品業界に止まらないと思います。日本でも一時期、半導体業界やIT業界、医薬品業界への異業種参入がありましたよね。それらの多くは失敗に終わっていますが、その理由はこの視点の欠如です。
いつ成果が出るかわからない基礎研究。
その評価は門外漢には難しい。
Q:その「視点」について、もう少し詳しくお聞かせください。
深尾:
簡単に言うと、せっかく相手方が持っている開発力を活かし、伸ばすことができていないんです。お金を使って技術者を揃えたのに、環境を揃えられないのです。ここでいう環境とは施設や設備ではありません。例えば、社内で会議をすると研究開発部門に対して、役員から「その研究はいつ実用化できるのか」、つまり「いつ利益を生むのか」を問い詰めてしまうのです。経営者の視点としては間違っていないのですが、基礎研究の分野ではこれが通用しない。
新薬の開発も同じで、「いつ形になるかわからない」のが基礎研究です。基礎研究はコストもかかるし、時間もかかります。だからといって、これをカットすると、技術系の企業の力は大きく低下します。一つの例ですが、旭化成で有名な薬であるエルシトニンも、開発中にある人が「もう開発を辞めろ」といったことがあるそうです。結果として、開発は続けられ、後に大ヒット商品になるのですが、その人は「あの発言は間違いだった」とふり返っておられます。それほど、基礎研究の評価は難しい。門外漢が簡単に判断出来るものではないのです。
経営危機に際して、コストカットの対象となりやすい研究開発
ポリシーなきコストカットは失敗に繋がる
Q:ただ、企業の経営難に際して、コストカットをする際に研究開発部門はその対象となりがちです。そうならないために、どんな評価基準で見れば良いのでしょう?
深尾:
まず、基礎研究と応用研究では、評価基準が違います。応用研究では、先程でたように「いつできるのか」「いつ売上になるのか」という評価の視点が欠かせません。
しかし、基礎研究では、そもそもそれがわからないんです。そこで「どれだけ独創性があるのか」「どれだけ研究者が必死に取り組んでいるか」で評価しないといけません。それができない、理解できないならば、基礎研究は育たないし、M&Aもうまくいかない。これは理系の研究開発だけではないんですね。営業だって、時間がかかるけれど利益率が高い営業もあれば、時間はかからないけれど薄利多売のスタイルなど、様々な営業スタイルがあります。これをどう評価し経営判断に活かすか、これは会社のポリシーなんです。
言いかえると、これはリスク管理です。先が読めない新薬の開発、基礎研究にどれだけのリスクをかけられるか。当たれば大きいけれど当たるかどうかわからない新規開拓の営業にどれほどの人材を投入するか。これは会社のポリシーです。大切なことは、「自分の会社にとっての投資リスクとは何か、リスクにかけられる投資をいくらにするか」を考えることです。
まず、毎月安定した売上が立つことが最も大切だというならば、そこに力を入れ、時間がかかる新規案件にかける力は少なくするでしょう。そうではない、新規案件を獲得し続けないと成長できない、そこが大切だというならリスクを負って新規開拓に力を入れる。バランスも大事ですね。
よくある「経営危機への対処」で多くの人がコストカットを挙げるのですが、そこにこのリスク管理の視点が無い場合がある。技術力が欠かせない企業で研究開発をカットする、地道で一見利益率が低そうな営業活動が欠かせないのに、それをカットして会社の屋台骨がゆらぐ。そんなケースは珍しくありません。経営危機を回避したいのに、傷を深めることになりかねないのです。
―お話の中で出て来た「経営危機の回避」。実は、深尾氏は、後のキャリアで複数の会社の経営危機に対処してきた経験があります。次回、後編では、その「経営危機回避のポイント」を伺いたいと思います。
取材・執筆:里田 実彦
関西学院大学社会学部卒業後、株式会社リクルートへ入社。
その後、ゲーム開発会社を経て、広告制作プロダクションライター/ディレクターに。
独立後、有限会社std代表として、印刷メディア、ウェブメディアを問わず、
数多くのコンテンツ制作、企画に参加。
これまでに経営者やビジネスマン、アスリート、アーティストなど、延べ千人以上への取材実績を持つ。