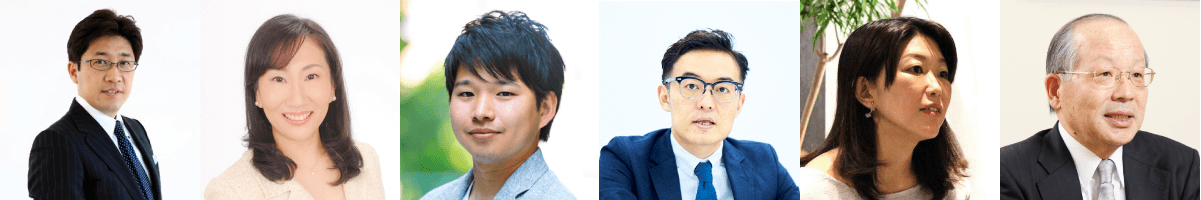会社には代表取締役社長をはじめ会長や役員、監査など実に多くの役職が存在します。その中で「顧問」という役職は、会社内でどのような役割を担っているのか、特にわかりにくい存在です。そこで顧問とは会社にとってどのような存在なのか、会社内での立場や経営上の責任についてなど詳しく解説していきます。
そもそも顧問とはどういった存在なのか?
顧問という肩書は新聞やニュースで目にする機会も多く、言葉自体には馴染みがあります。ですが、会社内での役割や仕事内容はあまり知られてはいません。顧問という言葉の意味を辞書で調べてみると「会社、団体などで、相談を受けて意見を述べる役、また、その人」と記載されています。
相談を受けて意見を述べる、つまり、顧問という存在は会社内で日常的にアドバイスを求められる立場ということです。豊富な専門知識や経験がなければ務まらないブレーン的存在ともいえます。よって顧問という立場は、主に知識や経験が豊富な会社の元管理職や元役員が担います。
経営上の高度なアドバイスを受けたい場合は、会社内部からの選任以外も一手です。その場合は、経営コンサルタントや弁護士、社労士といった高度な専門的知識を有する外部の専門家と「顧問契約」を結び、会社内に招へいすることになります。
会社内での顧問の立場や責任について
豊富な専門知識や経験から会社の諸問題についてさまざまなアドバイスを求められる顧問という存在に対し、会社内での立場や責任はどのようになっているのでしょうか?
会社内での立場は雑に分ければ「使用者」と「労働者」の2つです。社長をはじめ会社の経営を担当する立場の人が「使用者」、それ以外の人は「労働者」です。そこで顧問という立場はどちら側になるのかですが、実は「どちらでもない」のです。
顧問という役職は会社法には存在せず、設置するしないはその会社の自由です。また会社と委任契約を結び、報酬が支払われるとしても、株主総会で就任の是非を審議されるといったことや説明責任を問われることはありません。
顧問という立場から会社の経営にアドバイスをすることはありますが、顧問自体に意思決定の権限や議決権はありません。逆にいえば、会社の経営に対する責任も一切ありません。そういう意味で「どちらでもない」となるのです。
顧問の報酬や勤務実態とは?
顧問は会社法には存在しない立場のため、勤務形態や報酬の規定といったものも一切ありません。他の従業員と同程度の勤務を行う顧問や月に10日ほどの実働時間の顧問など、さまざまな勤務形態が存在します。
退任したトップ経営者を顧問に任命する慣習がある会社の場合、任命されてから1度も会社に顔を出したことのない顧問というのも存在するようです。
顧問の報酬は担当する業務内容や勤務形態などの諸条件によって会社ごとに決められています。その幅はピンからキリまでのようですが、一般的にはその会社の通常の役員よりは下になることが多いようです。
人事や労務の情報機関である産労総合研究所がおこなった2011年の役員報酬に関する実態調査では、顧問報酬の平均は常勤で年675万円、非常勤で年498万円となっています。
退任した会社OBを顧問にした場合は別ですが、弁護士やコンサルタントなど外部から招へいした顧問の報酬には相場感があるようですが、領域によって大きく異なるようです。
会社にとって顧問は必要なのか?
会社を退任した元経営トップが就くことの多い顧問。近年その役割や存在が不透明だとして海外の投資家らを中心に懸念が示されています。そもそも会社法にも規定のない顧問という存在は必要かどうか、疑問視されるのは当然です。
2015年に発覚した東芝の不正会計問題は、OBの顧問や相談役の影響力の強さが要因のひとつとされています。この問題をきっかけに会社の顧問や相談役が持つ影響力に対して株主から疑惑の目が向けられるようになりました。
実際、この年の6月の株主総会を前に数多くの企業が顧問・相談役制度を廃止しています。
こうした会社顧問や相談役への厳しい風当たりを受け、東京証券取引所は2018年より上場企業が顧問や相談役の役割を開示する制度を設けると発表しました。この制度によって今まで不透明だった顧問の業務内容や報酬の有無が明らかになると期待されています。
しかし上記の問題の一因である顧問制度の弊害をなくすためには、会社OBが顧問として籍を置き影響力を持ち続ける、日本独自の雇用システムの根本的な見直しが必要だといえそうです。
まとめ
会社にとっての顧問の立場、役割、責任などについて詳しく解説してきました。今まで「偉そうにしている顧問とはどのような存在なのか?」と疑問に感じていた人も顧問についてよく理解できたのではないでしょうか。
今、会社顧問に向けられている世間や株主の目は厳しいものです。ですので、これから先の顧問は、会社にとって本当の意味で有益な存在となることが強く求められます。