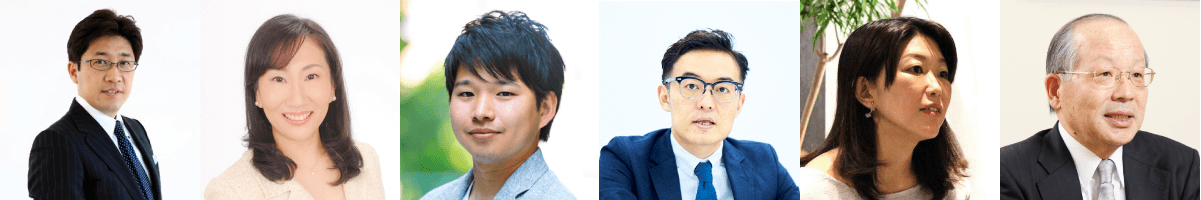ITベンチャーキャピタリストの先駆者は、目利き力をどう培ってきたのか?
フライヤー×サーキュレーションの「知見と経験の循環」企画第11弾。
経営者や有識者の方々がどのような「本」、どのような「人物」から影響を受けたのか「書籍」や「人」を介した知見・経験の循環についてのインタビューです。
今回登場するのは、安達俊久さん。伊藤忠商事株式会社に入社し、エプソン株式会社のプリンター輸出業務に従事。伊藤忠テクノサイエンス株式会社のECビジネス立ち上げなどを行い、2002年より伊藤忠テクノロジーベンチャーズ株式会社代表取締役社長として3本のファンドを運営。また、2011年から3年間、日本ベンチャーキャピタル協会会長を務め、現在は特別顧問の傍ら、複数社の顧問やアドバイザーをされています。
安達さんは、どのような思いでベンチャーキャピタル業界の礎を築いてきたのでしょうか?前編では、伊藤忠テクノロジーベンチャーズ設立の経緯から伺いました。
伊藤忠時代のシスコやオラクルとの取引がベンチャーキャピタル設立の原点
Q:伊藤忠商事に入社されてからの経緯をお聞かせください。
安達 俊久さん(以下、安達):
大学時代は電気・電子を研究していましたが、技術を実務に活かしたいと思い、伊藤忠商事に入りました。技術に詳しいということで、配属先は産業電子機器部という電子機器の輸出を行う部門でした。
当時は「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と称えられるほど、日本経済が高度経済成長期の絶頂にありました。私は1982年にロンドン駐在を経験していましたが、ちょうどその頃にプラザ合意が成立しました。すると、急激な円高で輸出が厳しくなり、90年代には輸出で儲けることは諦めないといけない状況になってしまった。
そこで思い浮かんだのが「逆転の発想」。「輸出がダメなら、アメリカの先端技術を誇るベンチャーの商品・サービスを日本市場で販売する権利を獲得しよう」と奔走しました。そして、Cisco(シスコ)やORACLE(オラクル)など多くの新興IT企業と取引するようになったんです。
そんなとき上司から、「こんな面白い会社と関係性ができたのなら、投資をすればもっと関係を強化できる」と提案されたのを機にアメリカの企業に投資をし始めたんです。その後、専門の会社をつくろうという動きが生まれ、ITに特化したベンチャーキャピタルとして「伊藤忠テクノロジーベンチャーズ」を2000年に設立することになりました。当時はITに特化したベンチャーキャピタルはほとんどない時代でした。
2002年に社長に就任し、13年間、ベンチャーキャピタリストとして日米のIT先端企業の盛衰を見る機会に恵まれたのです。
ネットスケープ創業者との出会い。絶好の投資先を逃した強烈な経験
Q:ベンチャーに投資しようという思いが強まるようになったきっかけがあったのでしょうか?
安達:
なぜここまでベンチャー投資に入れ込んだかというと、強烈なインパクトのある出来事が93年に起きたからなんです。それは世界で初めてWEBブラウザを世に生み出したNetscape(ネットスケープコミュニケーションズ)のジム・クラークとマーク・アンドリーセンとの出会いでした。伝説の起業家である彼らが、日本人に投資相談を持ちかけたのは、それが初めてだったそうです。当時はPC一人一台の時代もまだ到来していなかった。そんな中、彼らは「日本でもブラウザの市場展開を手伝ってほしい」と。PCでどう金儲けするのか、イメージすらできなかった私たちは、取引も投資も断ったのです。
ところが、その直後、Netscapeは96年にIPOを果たします。今となっては捕らぬ狸の皮算用ですが、もし投資していたら300~400倍のリターンが見込めたのに。逃した魚は大きかったですね。
ブラウザというのに目をつけた彼らには先見の明があったと思います。時を経てNetscapeはつぶれ、Microsoftなどに覇権を握られることになりました。ですが彼らがブラウザというまったく新しい概念を生み出したことで、インターネットが爆発的に世界中に普及し、時代を変えたのです。
非常に印象的だったのは、ジムが「俺が世界を変える」と語っていたこと。事実、Netscapeは当時、知名度も資金力もなかった、ただ情熱とアイデアはピカイチだった。「大々的な設備や基盤がなくても、アイデア一つでここまで世界が変わるのか」と圧倒されましたね。この経験から、日本の大企業よりもベンチャーへの投資に注力するようになりました。日本のベンチャーだけでなく、比率として3分の1程度は主にアメリカやイスラエルのベンチャーに投資していました。
ベンチャーキャピタル設立時の試行錯誤
Q:まさにインターネット黎明期からベンチャーキャピタル(以下、VC)に携わっておられたのですね。子会社設立にあたり、立ち上げ期ならではの試行錯誤はありましたか?
安達:
アメリカでなら、すでにベンチャーキャピタリストの先駆者はたくさんいました。ですが、VC業界の歴史が浅い日本では、VC業界のルールを定めるところからのスタートでした。ベンチャーキャピタルは、年間平均して10社ほど投資しますが、成功するのは1、2社というリスクの大きい世界。
失敗ももちろん色々ありましたよ。一番ひどかったケースは、投資先の社長に嘘をつかれたことですね。ベンチャーキャピタリストは投資を決める前に、その会社のことを綿密に調べます。ですが、完成していない技術をさもすぐ実現できると、徹底的に嘘を貫かれてしまったため、結果的に大きな損失を出してしまった。
とはいえベンチャーキャピタリストとしては、実現が難しそうなことであっても、本能的に、興味が湧き、可能性に賭けてみたくなるところがあります。それに、誰もが「いい会社だ」と称賛する会社に投資しても、大きなリターンは見込めません。だから大企業があまり手を出さないベンチャーに投資するので、リスクが大きいのは承知の上。ある意味、投資先にだまされるのも、生じうるリスクの一つという見方もできます。
金融系のVCだと、証券会社や銀行から出向した人から構成されているため、事業会社という観点で詳しいVCは当時はそこまでなかった。なので、会社を軌道に乗せるにあたっては、伊藤忠に元々いたIT業界に詳しい人材の知見を参考にした部分が大きかったですね。こうして親会社のリソースを活かしながら、投資の経験を増やす中で、目利きの力というか、良い企業を見極める基準を蓄積していったような感じです。
後編につづく
取材・インタビュア/松尾 美里
撮影/加藤 静
本の要約サイト フライヤーのインタビューはこちらから!
3万人ものベンチャー経営者と会われてきた安達さんは、
どんな信念を持ってベンチャーキャピタリストとしての道を歩まれたのでしょう?
そして、どのように投資眼を磨いてこられたのでしょうか?
プリンシプルを貫く安達さんの「見極め力」に迫ります。
専門家と1時間相談できるサービスOpen Researchを介して、企業の課題を手軽に解決します。業界リサーチから経営相談、新規事業のブレストまで幅広い形の事例を情報発信していきます。