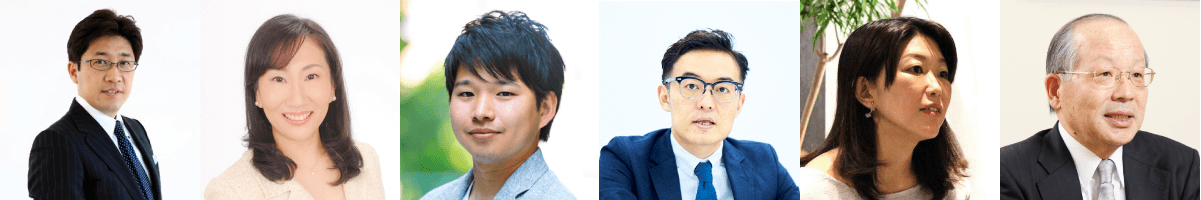いま、かつて日本を代表したブランドが苦しんでいます。伊藤氏が経営者として成長させたハイアール、アクアは、そもそも破たんした三洋電機の流れを汲む会社です。同様に、苦しむ日本企業は他にもあります。いま、日本企業はかつての輝きを失っているといえるでしょう。そこで伊藤氏は「日本覚醒」を叫んでいます。
海外で産まれ育ち、外資系企業で働き続けたからわかる、
日本企業がかつて放っていた輝きと現在の「意識不明状態」。
Q: 伊藤さんは昨年3月にハイアールグループ、そしてアクアのCEOを辞任され、半年の充電期間をおいて、現在のX-TANKコンサルティングを起ち上げられました。
伊藤嘉明氏(以下、伊藤):
もともとアクアでの契約は二年契約だったので、契約通りの辞任です。その後、半年ほど充電した後、具体的な名前は挙げられませんが、様々な企業から声がかかりました。たいてい、アジア系の外資系企業だったり、日本企業で経営が怪しくて再建が必要なところなどが多い。でも、そういうところにいくと、ハイアール、アクアでやったことのくり返しなのです。変化がない。前回最後に話したとおり、変化をしないことはリスクなので、そういったお誘いはすべて断りました。もともと数年前から「日本覚醒」と言っていたので、それにつながることをやりたいと思っていました。
Q:その「日本覚醒」ですが、いま、日本はどんな状態に見えているのでしょう?
伊藤:
はっきりいえば、意識不明状態ですね。このままの状態が続いたら死んでしまうかもしれない。でも、目が覚めたらすごいはずなんです。だから、起こそうというわけです。以前は、潰れた会社、潰れそうな会社を建て直すことが「覚醒」だと思っていました。でもそうじゃない。それだとわたし一人で一社しか起こせない。だったら、自分から変わりたいと思っている中小企業、能力はあるのにやり方がわからないベンチャー企業群を手伝う方が、一社の大企業を手伝うよりも価値があると思えたのです。
多くの人から、「大きな会社に行けば、安泰だし、実績からしてもいいだろう。なぜ独立なんだ」と言われました。でも、いまこれをやらないと後悔する。周囲から見ると難しそうだ、誰もが反対することにチャンスがあると思っているのです。コカ・コーラ時代の環境の仕事、デルでの負け犬軍団だった公共営業本部など、周囲から見ればやりたくない仕事をきちんとやって来たから今があるのですから。
Q:タイで産まれ育ち、アメリカの大学で学んだ伊藤さんから見て、日本企業はどの様に見えるのでしょう?
伊藤:
時代によって見え方は違います。子どもの頃、タイで生活していると、日本企業のロゴはあちこちで目にしました。それは光り輝いて見えたんです。まさに破竹の勢いだった70年代、80年代という時代でした。むしろ、タイにいたからこそ、その凄さがわかったのかもしれません。タイにいたからこそ、強く日本を意識していました。大学時代もアメリカでは寮生同士で夜中にデイベートを繰り返すのです。そこで、日本の凄さ、素晴らしさを一所懸命アメリカ人相手に説いていました。この頃は、アメリカ企業に元気がなくて日本企業が市場を席巻していました。それがすごすぎて、大学時代、ジャパンバッシングも目の当たりにしました。一方で日本企業の強さはリスペクトされていた。私は、カンバン方式をアメリカの大学で学んだくらいです。
経営が傾いた大企業に資金を投入して再生しても意味が無い。
なぜ危機に陥ったかを理解し、解決しなければまた、破たんする。
Q:ところが、最近は先程おっしゃられたように「意識不明状態」なんですね。
伊藤:
日本企業がかつてやってきたやり方、それが全否定されているのが、この10年ほどの流れだと思います。たとえば、最近話題の過剰労働です。高度経済成長期やバブル期など、あるいは私が働きはじめて部下を持つようになったときでさえ、残業は当たり前でした。有休なんて取るはずもない。
一方、私が働いた外資では、残業は無能がやること、部下を残業させる上司は部下を管理できない駄目上司なんです。私は働くことは好きですし、若い頃には徹夜で仕事をしたこともあります。でも休むときは休む。そういうトレーニングを受けてきたので、その後も、残業禁止と言いつづけましたね。ようやく、残業が多い、それで生産性が悪いと気が付きはじめた。昔から日本人は真面目で勤勉だと言われてきましたが、違うんじゃないか。生産性が悪いし、優秀ではないんじゃないか。そんなことが言われ始めているのが、いまなのです。
Q:そんな中で、かつて日本を代表したブランドが傾き、売却され、再生されて…という流れがあります。その一つである三洋電機をアクアという形で再生された伊藤さんからみて、どうやって日本を覚醒させようと思われていますか?
伊藤:
三洋電機がハイアールになって、アクアに生まれかわった。これも再生の一つの手段です。でも、いまでも自問自答しているのですが、無理して残す意味があるのか、と。駄目なら駄目でいいんじゃないか。潰れる会社には潰れる理由があるんです。そこに、多額の資金を投入して、ときには国が援助してまで残しても、根底にある「潰れた理由」を解決していないと再生したことにはならない。そういう企業体はまた潰れるのです。
再生事業では、お金を投入して再建します。でもそれではいけない。本当の再建事業、つまり覚醒事業は、経営状態を回復させるだけではダメなのです。事業を再建してもメンタリティが変化していないと同じことが繰り返される。駄目になった理由を見付けて、そこを直して、揺さ振っていかないといけない。揺さ振って目覚めさせる。日本再生ではなく、「日本覚醒」なのはそういう意味なのです。いま経営が傾いている企業は、銀行や他企業、時には国から資金が投入されて再生されるかもしれない。でもそれはゾンビのようなものです。おかげで危機感さえ生まれない。
いまだからこそ、自分が経験してきたこと、
学んだことを多くの日本企業に伝え、日本を覚醒させたい。
Q:その「覚醒」を三洋電機、つまりアクアで結果を出された伊藤さんだからこそ、大企業でそれをもう一度という声がかかるのも当然だと思います。
伊藤:
大企業のなかでやってきたからこそわかることもあります。いままでは正しいことを言えばそれでいい、だって正しいのだから、と思っていました。しかし、それでは敵が増える。社内には必ず変化に抵抗する勢力がいます。その社内での戦い、社内調整が仕事の八割だったりするのです。そんなものはどうでもよくて、戦うなら市場で戦うべきなのです。社内調整にエネルギーを使いたくない。だから、日本企業の圧倒的多数である中小企業と一緒に、日本を覚醒させたい。一つの大企業を変えることにも価値はありますが、いまは一社でも多くの中小企業を覚醒させていきたい。
私自身が経験してきたこと、なぜいま海外の企業がうまく言っているのか、日本企業がうまくいかないのか、そういうことをどんどん伝えていきたい。いまの状態に疑問や不満があって、現状を良い方向に変えたい人、変わりたい人、答えが欲しい人、そういう人に一人でも多く伝えていきたいといま、感じています。
Q:いまから五年後、あるいは十年後、伊藤さんは何をしているでしょう?
伊藤:
いま実は、私はX-TANKコンサルティングだけではなく、他にも複数の会社の経営にも携わっています。経営者なら複数の会社を持つ人もいるでしょうが、いままでの日本では副業は基本的に認められませんでした。それが変わりつつあります。3年後には、会社員だけれど副業で会社を経営しているという人も増えているかもしれません。これは、チャレンジできる環境になってきているということだと思います。私はそういう環境を推進したりしつつ、きっと日本を離れてアジアにいるでしょうね。生まれ育ったタイに貢献したいという気持ちもあります。そこで子どもの頃に見た、光り輝いていた日本を取りもどしたい。いま、日本の地位は東南アジアでも急速に地盤沈下しています。覚醒した日本企業があり、それを改めてアジアで伝えていきたいですね。
Q:最初に「仕事において、父親の影響が大きい」とおっしゃっていましたが、その点、いまお父さまの仕事ぶりに追いついたというような意識はあるでしょうか?
伊藤:
父の背中を追うのは、もう随分と前にやめました。いまは全く違う道を走っていると思っています。同じことをやっていたとしても、父とは時代も違えば環境も違うので、比較はできないですよね。だからいつしか、追い掛けているという意識はなくなりました。
最近思うのは、若い頃、体力もあったし馬力で仕事をした面もあったのですが、最近はそうではなくなっていると感じます。自分自身が経験してきたこと、学んだことをきちんと伝えていく必要性をとよく感じるようになりました。だからこそ、いまあえて独立という変化を選んだんです。妥協して安定した立場を得ようとすればそれはいつでもできる。そうならないように、いまも試行錯誤をしています。
―タイで産まれ育ち、アメリカで学んだ。グローバル規模の外資系企業で経験を積み、実績を残し、傾いた日本企業の再生でも結果を残した。そんな伊藤さんだからこそ、「変化をしないことがリスクだ」「差異化しろ」「目を覚ませ」という言葉に深い説得力があると感じられました。また、2年後に同じテーマでお話を伺うと、変化をお聞きできそうです。そのチャンスがあることを願います。
取材・執筆:里田 実彦
関西学院大学社会学部卒業後、株式会社リクルートへ入社。
その後、ゲーム開発会社を経て、広告制作プロダクションライター/ディレクターに。
独立後、有限会社std代表として、印刷メディア、ウェブメディアを問わず、
数多くのコンテンツ制作、企画に参加。
これまでに経営者やビジネスマン、アスリート、アーティストなど、延べ千人以上への取材実績を持つ。