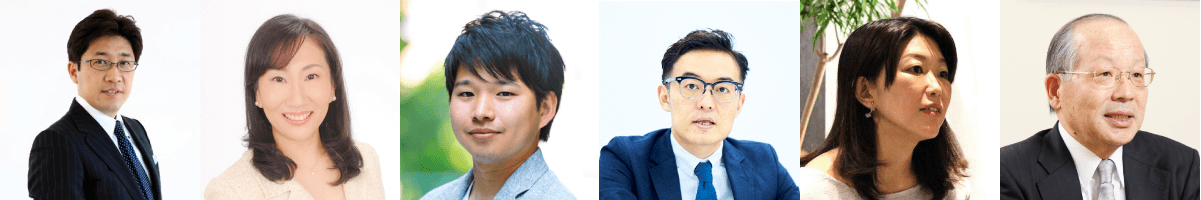専門家によるリーガル相談。今回は、受託者として、ノマド、個人事業主の多くは避けることができない、委託者側としても企業が外部人材を活用時に必要となる「業務委託契約」を取り上げます。その中でも重要な条項として、知的財産権の帰属、損害賠償について前編、後編にて解説します。
全てのビジネスパーソンが知っておくべき、「業務委託契約書」
現代の企業活動においては、その事業活動の至るところでコンピューター・システムを利用していますが、そのシステムの開発、保守および運用は、他社に委託することが多くなっています。また、外部業者にコンサルティングを委託する場合や、経営の効率化の観点から、一定の業務をアウトソーシング場合もあるでしょう。さらに、最近では、クラウドソーシングで、仕事を受発注するケースも増えてきています。
このように、様々な業務を他の者に委託するなかで、その業務内容等を定めた「業務委託契約書」は、ほぼ全ての企業において何らかの形で締結されていると言っても過言ではない状況となっています。
また、受託者としても、独立コンサルタントとして知見やノウハウを提供して対価をもらう場合、業務委託契約は避けられません。多くの独立コンサルタントや個人事業主が、事前に適切な契約を締結できていなかったことから、ただのノウハウの流出になってしまったり、報酬額を超える損害賠償を請求されてしまったりする事例があります。この契約の中身について理解して適切に交渉ができるようにしておくことは独立の第一歩といえます。
業務委託契約書の重要な条項は?
業務委託契約書における重要な条項としては、委託内容、対価、再委託の可否などがあげられますが、特に重要であり、しかも交渉の過程においてよく問題となるのは、知的財産権の帰属および損害賠償に関する条項です。
そこで、今回は、「業務委託契約書」における「知的財産権の帰属」のチェックポイントおよび交渉上の留意点やその落とし所について解説したいと思います。
なお、以下では、委託者が受託者に提示する場合を【委託者⇒受託者】、受託者が委託者に提示する場合を【受託者⇒委託者】と記載します。
それでは、具体的に見ていきましょう。
知的財産権の帰属について【委託者⇒受託者】:成果物の知財は委託者(依頼者)のものになるとは限らない?
(提案すべき条項案)
第●条 知的財産権
1.本件業務の過程で生じた知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、これらの権利を取得しまたは登録等を出願する権利、その他のノウハウおよび技術情報等を含む。著作権については著作権法第27条および第28条に定める権利を含む。)および成果物に含まれる知的財産権は、成果物の納入と同時に委託者に移転するものとする。
2.受託者は、成果物その他本件業務の過程で作成された著作物について、著作者人格権を行使しないものとする。
(解説)
委託者がお金を支払う以上、成果物の知的財産権は委託者が当然に取得できると勘違いをしている方もいらっしゃるかもしれません。しかしながら、法律上は、特許権は実際に発明を行った発明者に、著作権は実際に著作物を創作した著作者に帰属することが原則です。
したがって、契約書に何も規定していない場合には、委託した業務に伴って発生した知的財産権は、委託者側に移転しないのが原則です。そのため、委託者が知的財産権を確保するためには、知的財産権が移転する旨を明確に定めておく必要があります。
この点、著作権については重要な注意点が2つあります。ここは、見落としがちな点となりますので、特に意識して確認するようにしましょう。
「全ての著作権を譲渡する」と規定しても対象外と推定されるものがある
まず1点目は、知的財産権の移転を規定するにあたっては、「著作権法第27条および第28条に規定する権利を含む」と明記しておく必要があるということです。これは、著作権法第61条第2項において、「著作権を譲渡する契約において、第27条または第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。」と規定されているためです。第27条の権利とは、翻訳権、翻案権等であり、著作物を翻訳、変形等する権利が想定されています。また、第28条の権利とは、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利のことをいいます。これは、例えば、ある会社(A社)が開発したシステムをベースとして、他の会社(B社)が新たな著作物(二次的著作物)と言えるものを開発した場合、その新たな著作物については、それを開発したB社のみならず、もとのシステムを開発したA社もB社と同一の権利を有するというものです。
たとえ「全ての著作権を譲渡する」と規定しても、上記2つの権利は、譲渡が明記されていないと譲渡の対象外と推定されてしまいますので、注意しましょう。
著作者人格権とは?納品されたものを変えることができなくなるリスク
2点目は、「受託者は著作者人格権を行使しない」旨を定めておく必要があるということです。著作権法第59条において、著作者人格権は著作者の一身に専属し譲渡することができないと規定されています。著作者人格権とは、公表権、氏名表示権および同一性保持権の3つの権利を意味し、そのうち同一性保持権は、「著作者は、その著作物およびその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。」(著作権法第20条第1項)と規定されています。上記の著作権法第27条の権利の譲渡を受けたとしても、この同一性保持権を行使されると改変ができなくなるおそれがありますので、委託者としては、受託者に対し著作者人格権を行使しないよう誓約させておく必要があります。
以上のとおり、著作権の譲渡に関しては、①著作権法第27条または第28条に規定する権利の譲渡を特に規定し、②著作者人格権の不行使の特約を規定するという2つの処理を伴って初めて適切に権利を確保したと言えますので、業務委託契約においてはこの点を明記しておく必要があるということを、常に頭に入れておくようにしましょう。
特にベンチャー企業においては、ファイナンスやM&Aの際のリーガル・デュー・ディリジェンスや株式公開の引受審査にあたり、業務委託契約書においてこのような手当てがなされていない場合には、受託者との間で上記2点に関する確認書を取得してもらうなどの対応を要請される場合もあります。このような対応は相手方のある事項であり、こちらのスケジュールどおり達成できる保証もありませんので、ファイナンスや株式公開のスケジュールとの関係で問題となる可能性も否定できません。したがって、自社が委託側である業務委託契約書においては、特に上記の著作権の規定については注意するようにしましょう。
【受託者⇒委託者】:知財を移転する上で留保する範囲を検討する
(提案すべき条項案)
以下の条項を、上記条項案の第2項として追加することが考えられます。
第●条 知的財産権
2.前項の定めに拘らず、①受託者が本件業務の着手前から有している知的財産権ならびに②成果物と同種のシステムに共通に利用されるノウハウ、ルーチンおよびモジュールに関する知的財産権は受託者に留保され、受託者はこれらを利用して自由に他のシステムの開発を行うことができるものとする。
(解説)
受託者としては、知的財産権は一切移転しないとしておくことが最も有利です。
しかし、現実的には委託者に受け入れられないことが多く、また委託者の依頼を履行する過程で発生した知的財産権は受託者には使い道がない場合もあります。
そのため、原則として知的財産権は委託者に移転するとした上で、一定の範囲で留保する必要はないかを検討することが重要となります。具体的には、委託業務の着手前から保有していた知的財産権(上記①)や他の案件に流用することが予想される知的財産権(上記②)については、委託者に移転せずに留保される旨を規定することを検討した方が良いでしょう。
【委託者⇒受託者】: どの権利の譲渡を受けておく必要があるか?譲渡を受けない場合、どのような対応をとるべきか?
(提案すべき条項案)
上記条項案の第2項に下記下線の文言を追加することが考えられます。
2.前項の定めに拘らず、受託者が本件業務の着手前から有している知的財産権(※ならびに成果物と同種のシステムに共通に利用されるノウハウ、ルーチンおよびモジュールに関する知的財産権)は受託者に留保され、受託者はこれらを利用して自由に他のシステムの開発を行うことができるものとする。但し、かかる知的財産権が成果物に含まれている場合、委託者は、当該知的財産権に関する使用等の対価を支払うことなく、成果物を自由に利用(複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利用を含む。)することができるものとする。
(解説)
まず、受託者が委託業務の着手前から保有していた知的財産権(上記①)については、委託業務の履行の有無にかかわらず受託者が独自に保有していたものといえる上、受託者が今後の事業において使用することが想定されるものでもありますので、この権利が受託者に留保されるとするのはやむを得ないところがあります。
一方、成果物と同種のシステムに共通に利用されるノウハウ、ルーチンおよびモジュールに関する知的財産権(上記②)については、委託者が、今後、成果物を使用してビジネスを展開していくにあたり、この権利を自由に使用できるようにしておく必要性が高い場合もあります。
したがって、上記②については、受託者に留保させず、譲渡を受けておく必要がないか、検討しておくことが重要となります。
権利の譲渡を受けておくべき場合には、上記②は受け入れない(すなわち、※の箇所は削除する)ことになります。加えて、委託者としては、納入を受けた成果物は自由に使用できるようにしておく必要があります。
そこで、受託者に留保された知的財産権については、自由に利用することができるよう、下線部分の但書を規定しておくことが重要です。
今回は、業務委託契約について、委託者及び受託者の立場で注意する点のうち、知的財産権について解説をしました。(後編)は、損害賠償について取り上げます。

(長尾 卓氏 AZX総合法律事務所 パートナー弁護士)
ベンチャー企業のサポートを専門としており、ビジネスモデルの法務チェック、利用規約の作成、資金調達、ストックオプションの発行、M&Aのサポート、上場審査のサポート等、ベンチャー企業のあらゆる法務に携わる。特にITベンチャーのサポートを得意とする。趣味は、バスケ、ゴルフ、お酒。

(小鷹 龍哉氏 AZX総合法律事務所 弁護士)
弁護士になって以来、適法性チェック、各種契約関係法務、ファイナンスサポートなどを通じて、ウェブサービス、スマートフォンアプリサービス等をメインとするベンチャー企業の挑戦を幅広くサポートしている。特にファイナンスに強い。
ノマドジャーナル編集部
専門家と1時間相談できるサービスOpen Researchを介して、企業の課題を手軽に解決します。
業界リサーチから経営相談、新規事業のブレストまで幅広い形の事例を情報発信していきます。