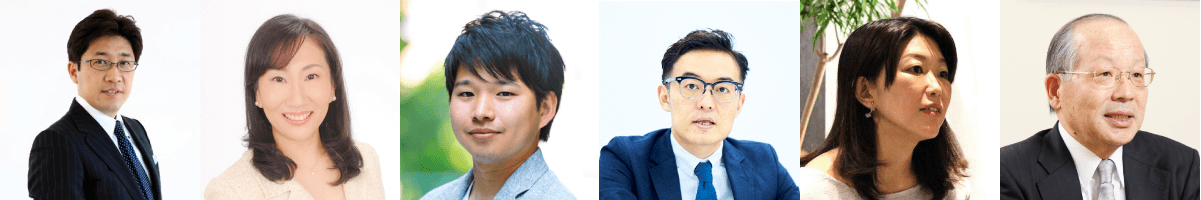日本アーンスト・アンド・ヤングコンサルティング、日本コカ・コーラ、デル、レノボ、アディダスジャパン、ソニーピクチャーズ エンタテインメント、ハイアールアジアグループ(現アクア)… 共通点と言えば、外資のグローバル企業であることだけです。しかし、業種も全く異なるこれらの会社で働いただけでなく、実績を残し、経営者として高い評価を受ける人物がいます。それが、伊藤嘉明氏です。ある種、異形とも言える経歴を持つ伊藤氏はいま「日本覚醒」を掲げて、経営コンサルタントとして活躍を始めています。
タイでモータリゼーションを牽引した父の背中を見て、仕事を覚えた。
自動車事故がなければ、間違いなく自動車業界で働いていた。
Q: 伊藤さんというと、名だたる企業で要職を努められ、その後、あの三洋電機を買収したハイアールアジアグループでアジア地区統括CEO、さらに三洋を受けつぐアクア株式会社のCEOを兼務され、昨年3月に辞任されています。現在は、X-TANKコンサルティングを自ら起業されていますが、この経歴には驚かされることがいくつもあります。まず、名だたるグローバル企業ばかりであること、そして業種がバラバラだということです。
伊藤嘉明氏(以下、伊藤):
そもそもの話をすると、私は、父の仕事の関係でタイで生まれ、タイで育ちました。父はタイでモータリゼーションを興したといわれるビジネスマンでした。日系の商社だったのですが、いわゆる日本の大商社から派遣されたサラリーマン経営者ではなく、自ら株式を保有する生粋の経営者でした。その父を見て育った影響は大きいと思います。アメリカの大学を卒業した後には、父が経営するオートテックタイランドで共に働きました。そこで父に仕事のイロハを叩きこまれたんだと思います。
Q:その後、再度アメリカに行かれて、MBAを取られていますね。
伊藤:
マーケティングを学びたくてアメリカの大学に進学したのですが、卒業後に父と仕事をしてもっと勉強しなければダメだと感じたんです。そこで、サンダーバード国際経営大学院ビジネススクールで学んだのですが、父の仕事の影響もあって自動車が好きで、自分自身自動車業界に進みたかった。実際に、ダイムラークライスラーのインターンにも選抜されたのです。これが全米でも10名しか選ばれない狭き門。世界有数の自動車メーカーの幹部候補生です。ところが、そんな時に自動車事故に遭ってしまった。その影響があり、自分で自動車を運転するのが怖くなったんです。それでは、自動車業界では働けないと思いました。この事故さえなければ、間違いなく、自動車業界に進み、いまも働いていたでしょうね。
MBAを取ったからすごいのではなく、
MBAを取るためにリスクを取る覚悟がすごい。
Q:そこで実際には、日本アーンスト・アンド・ヤング・コンサルティングに就職されています。
伊藤:
MBAを取ったときに、多くの企業からオファーをいただきました。先程のダイムラークライスラーを含むいわゆるビッグ3だけでなく、いろんなところからお声をかけていただいたのですが、どうにもしっくりこない。自動車業界以外を考えていなかったので、それ以外となったときにイメージが湧かないのです。周囲を見ると、いわゆるMBAを取った人間が描くキャリアがあって、その中に経営コンサルティング業界があった。経営コンサルならいろんな業界を勉強できる。そこで自分が進むべき道を探そうと考えたわけです。次に転職した日本コカ・コーラはアーンスト・アンド・ヤング時代のクライアントですから、それは叶ったことになりますね。
Q:日本コカ・コーラでは環境経営という、いまでこそ当たり前の言葉ですが、当時は影も形もなかった概念を形にするという仕事をされました。またその後のデル、レノボなどでは、若くして経営に深く携わられています。アメリカではMBA取得者は最初から経営幹部候補生として働くことも多いと思いますが、そこは文化が違うのでしょうか。
伊藤:
ただMBAを取ったからすごいかというとそうではないと思います。私もそうでしたが、アメリカなんかだと、学費や生活費を借金でまかなってMBA取得をする人が大半です。日本から会社の費用で学びにいっている人とは、全く覚悟のレベルが違うのです。そもそもビジネススクールに行き、MBAを取るだけで、二年間、社会に出るのが遅れるわけです。それもハンデになる。それだけの覚悟をもってMBAを取る人は違いますね。
お金をもらって働く以上、プロだ。
プロならば、残した実績で評価される。
Q:それだけ、経営者となるだけの覚悟があるということでしょうか。似たような事例で、アメリカでは、プロ経営者というか、複数の会社を経営者として渡りあるく人がいます。伊藤さんの経歴でも、経営者として、業界も異なる会社を渡り歩かれているようにも見えます。人によっては、アメリカ型のプロ経営者に見えるかもしれませんね。
伊藤:
いろんな業界を渡り歩いているので、何の専門家かわからないとは言われます。ただ「プロ経営者」という言葉にも違和感がある。お金をいただいて働いている以上、それはもうプロなんです。わざわざ「プロ経営者」と”プロ”を付ける意味が無い。例え、新入社員であっても、給料をもらっているプロだと思います。おそらく、”プロ”という言葉の意味が”スペシャリスト”に近いニュアンスになっているのでしょう。
実際、私のように、飲料からパソコン、スポーツアパレル、エンタテインメント、家電と全く違う業界を渡りあるいている人間は珍しいようですね。ある有名なヘッドハンティング会社の元日本支社長の方からは「あなたの履歴書は汚いから日本では評価されない」と言われたことがあります。同じ業界に三年といないのですから。でも、そう言って私を酷評した人の上司にあたる米国本社の役員が、ソニーピクチャーズのオファーを持ってくるのですから、おかしなものです。結局、結果を残してきたかで評価される。それがプロなのでしょうね。
異なる業界を経験してきた経歴で気付いた、
自分がそこで何ができるか、という発想。
Q:日本では、どこか経営のプロ、スペシャリストへの懐疑というか、外部から経営者が招かれて…という流れを嫌がる雰囲気がありますね。
伊藤:
僕自身、言われました。外からやって来て、何がわかる、と。それこそ、コカ・コーラ、デル、レノボ、アディダス、ソニーピクチャーズエンタテインメント、ハイアール、全部で言われたと思います。
Q:そうなると、新しい環境でのスタートが、マイナスから始まるわけですよね。それをどうやって克服していくのでしょう?
伊藤:
コカ・コーラ時代ですが、入社してすぐは、コミュニケーションマネージャーとして、オリンピック関連の広報を担当していました。しかし、オリンピックが終わるとやることがない。そこで、環境関連を担当することになった。当時は、会社の中で環境関連の仕事に携わるということは、ビジネスの本流ではありませんでした。担当されている先輩方もセミリタイアしたような方々が多かったんです。なかには不本意ながらやっているという人も少なくない。そういう先輩方の上に立たなければならなくなった。
彼らにすれば、私のような若僧が上司だなんて面白くない。「リサイクル法について、見解をお聞かせください」なんて突き上げてくるんです。付け焼き刃で語っても、先輩方の見識に勝てるはずがない。先輩方は何年分ものアドバンテージがあるわけです。そこに僅かな勉強で勝とうと思うのは、ある意味、失礼だと思うんです。ならば、先輩方が持っていなくて、自分が持っているものはなんだと考えた。それはアメリカでMBAを取った経験があり、マーケティングを学んできたということだと。
その視点で、それまでやっている環境への取組を見ると、工場を緑化したり、植樹したりということばかりだった。それは大事なのですが、コカ・コーラという世界でも有数のコンシューマグッズの企業ならば、もっと大きなレベルで取り組むべきだ。企業ブランディング、「環境経営」という視点でとり組むべきだと訴えたんです。そうして、上層部にも掛け合って、コカ・コーラ初の環境報告書を作るなどの実績を挙げていきました。
学生の頃、野球をやっていたのですが、ポジションごとに役割が違う。それと同じで、自分はこのチームでは、何ができるか、何をすべきかを考えていったのです。
Q:その後、デル、レノボというパソコン業界に転職されていますが、そこでもある種、よそ者だったわけですね。
伊藤:
それをいうと、もともと自動車業界に進むつもりだったので、コカ・コーラだってよそ者だったのです。環境だって、専門ではなかった。そもそも、その道で何年もやられている専門家に簡単には勝てないです。でもそのままだと、単に年功序列になってしまってつまらない。情報は常にアップデートされていきますし、時代も変わっていく。だから、自分なりにテーラーメイドしていくのです。その場に合わせて、自分を仕立てていく。コカ・コーラで自分がやったのは、環境と経営を結び付けたこと、それがマーケティングを専門とする僕のエッセンスだったのです。
―異なる業界を渡りあるきながらも実績を残してきた背景には、プロとして当たり前の意識、覚悟があったことが伝わってきます。そして、複数の企業を渡りあるく中で、磨かれていったのが、自分がそこで何ができるかを考え、自らをテーラーメイドしていくことでした。それが、次回詳しくお話しいただく”差違化”という力なのです。
(中編へ続く)
取材・執筆:里田 実彦
関西学院大学社会学部卒業後、株式会社リクルートへ入社。
その後、ゲーム開発会社を経て、広告制作プロダクションライター/ディレクターに。
独立後、有限会社std代表として、印刷メディア、ウェブメディアを問わず、
数多くのコンテンツ制作、企画に参加。
これまでに経営者やビジネスマン、アスリート、アーティストなど、延べ千人以上への取材実績を持つ。