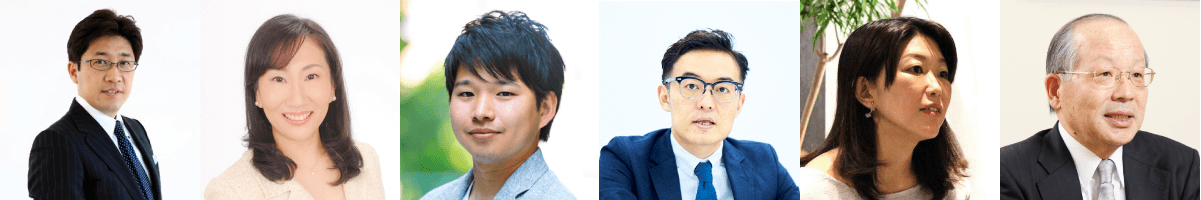フライヤー×サーキュレーションの「知見と経験の循環」企画第7弾。
経営者や有識者の方々がどのような「本」、どのような「人物」から影響を受けたのか「書籍」や「人」を介した知見・経験の循環についてのインタビューです。
今回登場するのは、IT業界のご意見番としても著名な有賀 貞一さん。
野村電子計算センターに新卒で入社後、NRI(野村総合研究所)最年少取締役へ。CSKに転籍後は、金融システム事業本部長、公共システム営業本部長、SI事業本部長など歴任し、株式会社ミスミグループ本社の代表取締役副社長へと複数社を渡り歩いてきました。現在は、複数社の顧問として、スタートアップのコンサルティング、人材育成に従事されています。
複数社の役員を歴任してきたIT業界の重鎮である有賀さんは、どんなキャリアの転機を乗り越え、どんな知見を活かしてきたのでしょうか。
日本におけるコンピュータの黎明期に立ち会う―独学でプログラミングを習得し、野村電子計算センターへ―
-まずは有賀さんの若手時代のお話を伺いたいと思います。どんな心持ちで社会人生活のスタートを切られたのでしょう。
有賀 貞一さん(以下、有賀):
高校時代、日本最初の電子計算機が野村證券本社ビルに運び上げられている写真を新聞で見て、将来この計算機を使った仕事がしたいと思いました(1955年、日本初の商用電子計算機が、米国から株式会社東京証券取引所と野村證券株式会社に導入された)。とはいえ、当時はコンピュータ分野について学べる学部は全国に2カ所新設されたばかり。そのため、コンピュータ分野の学部の教授も他学部から引き抜いて集めたような形です。思ったような勉強は難しいように感じ、コンピュータは独学にして、大学は就職にも有利なところにしようと思い、一橋大学の経済学部に入りました。すると、運命のいたずらというべきか、一橋の教授陣がコンピュータクラブを創設することになって。学内にたった一台の電子計算機を使えるなんてまたとない機会だと思い、一期生で入部し、全国のコンピュータクラブ組織化後に委員長を務めることになりました。
大学1年生の頃、IBMに内定した先輩からひと月に6日間徹夜してコンピュータで月末決算処理をするアルバイトをしないかと誘われました。初任給が3万円の時代に、日当1万円という好待遇だったので、卒業までずっと続けていました。そのため、学生としてはかなり豊かな生活をしていたのですが、逆に就職すると収入が激減して生活が困窮してしまいました。
当時はIT業界の本もないので、雑誌や海外の書物から最新情報を仕入れるしかなかったんです。プログラミングも、今で言うスマホのアプリ開発のような経験を積み、実地で覚えていきました。
後になって思うと、一橋大学の経済学部を選んでいたおかげで、プログラミングに特化せず、ITの利活用について考える機会を得ることができました。それがその後のキャリアに活きてきたのだと思います。
新卒で入社したのは当時できたばかりで従業員100名程度の野村電子計算センター。ベンチャーなら大企業よりは早く偉くなれるだろうと思ってね(笑)何より大学時代に積み上げてきた専門性が活かせるうえに、やりたいことの方向性が合っていたのが決め手でした。プログラミング経験がすでにあるからと入社前から出入りしていましたし、そのためもあって私だけ新入社員研修も受けさせてくれなかったけれど(笑)
-学生時代からまるで独立されていたような印象を受けます。起業の道は考えなかったのですか?
有賀:
当時はまだ起業が一般的な選択肢ではなかった。それに私の本来の性格は、戦略参謀タイプ。自分で先陣を切って立ち上げるという感じではなかったんです。
入社後は、タクシー会社の給与計算パッケージの開発に携わりました。汎用性のあるシステムづくりを目指したものの、当時はパッケージ化に耐えうる技術が育っておらず、採算性が悪くて頓挫してしまった。実は3年目のときは行き詰っていた時期で、仕事をやめようかと考えていたくらい。
そんなとき、目をかけてくれていた当時の専務が「本社(野村証券)のシステム管理部に出向しろ」と支持してくれた。新システム開発のプロジェクト推進の仕事で、PMO(※1)の先駆けといってもいい。プロジェクトの終盤には、ニューヨーク駐在員事務所長となり、ニューヨークでシステムの再構築から、海外ネットワークの運用、オフィスの移転まで一手に引き受けた4年間でした。途中でユニオンの業務妨害に遭うなど困難もありましたが、よい経験を積むことができたと思います。
(※PMO:組織内における個々のプロジェクトマネジメントの支援を横断的に行う部門や構造システムのこと。)
NRIグループ最年少取締役へ-大規模プロジェクトの受注に向けて孤軍奮闘の日々-
-専門職のような立場で入社されたのに、その後はマネジメント的な立場を任されてきたのですね。
有賀:
私のようなキャリアは非常に珍しいでしょうね。技術の最先端のトレンドにふれるのが好きだったこともあり、常に新しいことをさせられる立場でした。
1988年の野村総合研究所と野村コンピュータシステムとの合併でも、次長の立場で密に議論に関わるという貴重な経験を得ることができました。この合併についても、ここではいえませんがいろいろなドラマが裏側ではありました、それらを当事者として関与することができたのは貴重な経験です。そこで、野村コンピュータシステム社長を務めていた松浦正輔さんから「実力主義による意思決定」を学んだのは大きな収穫でした。彼は戦略思考の塊みたいな方。かなりのエスタブリッシュ企業であった野村證券から来られたにもかかわらず、年功序列や従来の慣行にこだわらず、実力・実績を尊重し、実力者や頭角を現しそうな若手をどんどん重用したのです。おかげで私自身、41歳のときにNRIグループで最年少取締役就任というチャンスをいただき、合併でそれまでの300人規模から一気に2000人規模の会社になるという変化の時期を肌で感じることができました。だから急成長するベンチャー企業の経営者が、自分の予想を超えて組織が大きくなってしまったりしたときに感じるような悩みもよくわかるんです。
1994年から公共システム部長と兼任となり、1500億円規模の巨大プロジェクトを進めようとしていました。「NRIは大規模プロジェクトによって人材を育てるべきだ」という信念を持っていたからです。97年には入札に漕ぎつけましたが、周囲からは「黒字になるかも定かではないしリスキー」と散々言われました。受注のために邁進する私と、受注しても社内リソースが足りずリスクが高いと反対する他の役員との間で役員会も紛糾し、まさに孤軍奮闘の日々。大上段から客観的な分析ばかりする役員とは、特に喧嘩をよくしました、分析ばかりで当事者意識がないことが非常に腹立たしかった。結局受注を決め、優秀な担当者をアサインしたタイミングで会社を離れました。
CSKを経てミスミグループでの挑戦-CSK大川会長、ミスミ三枝社長と働く-
-そこからCSKに移られたのですね。
有賀:
CSKに移ったのは、こうした前向きでない風土に面白味を感じられなくなったことが影響しています。創業者の大川会長や福島社長(元野村證券副社長)が、前々から「CSKにきてほしい」と声をかけてくれていたことも理由の一つ。もともとの出会いは、ニューヨークで大川会長を案内したのがきっかけでした。初めて会った時、大川会長は会社を上場したタイミングでしたが、大きなテーブルに向かい合ってお話をした際、当時は一駐在員にすぎなかった私の話を非常に熱心に聞いてくださり、一言一句もらさず大学ノートに書き留めていた姿が印象的でした。上場企業の社長でありながら、ここまで勉強熱心で謙虚な姿勢をみて素晴らしい経営者だと感じました。
移った当時はバブル崩壊に伴い、金融業への派遣型ビジネスが崩壊してまさに「底」の時期でした。昇り竜みたいな会社より、これからはい上がっていく会社に行ったほうが面白いと思ってね。給与が下がるのもいとわなかった。
CSKの金融部門も売上が落ち込んでいて、新入社員も敬遠しているような部署だったのですが、だからこそ彼らに「金融部門に行きたい」と思わせようと闘志が湧いた。山一證券が倒産した直後には、人材を採りたい一心で、倒産した翌日に山一情報システムの社長に会いにいったこともあります。そこから数年で金融部門を大きく回復につなげることができた。
CSKの生産性向上委員会では、作業の「見える化」や標準化を目指すため、ソフトウェアの機能規模を測定する「ファンクションポイント」という手法の採用に踏み切るなど、面白い経験を積むことができました。ただ、CSKが不動産融資に力を入れすぎて本業がおろそかになっていくにつれ、非常に儲かるわけですが危ない商売だなと思い、会社の方向性が私と合わなくなっているように感じました。そこで徐々に転身を考えはじめ、ミスミグループの顧問と兼任するようになり、2008年にミスミに完全に移籍し、ミスミ本社の副社長に就任しました。当時のミスミグループ本社代表取締役社長CEOの三枝さんは一橋大学の先輩にあたります。ミスミでは流通・物流・情報システムを担当する事業プラットフォーム本部長と兼任することになりました。
NRIからCSK、そしてミスミへと、決して順調に移行したのではなく、節目ごとにドラマがあったんですよ。どこの会社でも私はよく社長や上司とぶつかっていました。実は喧嘩別れが多いです。ミスミも最後はシステム化の方針で折り合わず、退職しました。
-ミスミで流通・物流という新たな分野に挑戦されたのは、どんな思いがあったのでしょうか。
有賀:
宅配業の会社を除いて、一般的な会社に流通や物流の専門家はほとんどいないので、挑戦しがいがあると思ったんです。また、流通・物流は改善余地がある宝の山だと思っていましたから。
複数社の経験で実感した、知見の「抽象化」の重要性。一分野の専門家にとどまっておくのはもったいない
有賀:
久保田さん(株式会社サーキュレーション代表取締役社長)を紹介されたのがきっかけで、複数社に対して顧問というスタイルで働くことになりました。サーキュレーションにも立ち上げ時から関わっています。
現在はクラウドソーシングのリアルワールド、メディア事業のメディアコマース、クラウドコンピューティングのFIXERやセールスフォース、そして情報セキュリティーの会社の顧問を並行しています。こういう業種をカバーしていれば、常に最先端のIT利活用をカバーできますからね。
-現在は複数社の顧問をされていますが、一社にフルコミットするときと、どんな違いがありますか。
有賀:
今の働き方のほうが、知的好奇心を満たすことができます。そして、複数社、複数業界で自分の価値を発揮して働くためには、自分の知見や経験の抽象化が重要だと思っています。
ミスミに行ったことでNRI、CSKでの知見や経験を言語化、抽象化してまとめ直すことができたのは、非常に役立っています。この辺りではミスミの三枝さんの考え方にも影響を受けています。抽象化できれば、それをマニュアル化、標準化して、違う業種でも活かすことができる。若い世代の育成に関わっているのも、30代の頃にこうした機会があったほうがいいと考えているからです。
例えば、流通業界の在庫管理の考え方は、金融業界にも取り入れることができます。極端に言えば、預金を「在庫」だととらえると共通項が見えてくるでしょう? 業務全体の流れの中で、本質は何かを考えることが必要ですね。ケーススタディーで事例の引き出しを増やしておけば、一分野の専門家にとどまっておくのはもったいない。
業界ごとの知識は、ググれば一発で得られますよね。若い人たちの人材育成に関わっていて不思議に感じるのは、「なぜ、ググる数分の手間を惜しむのか?」ということ。昔は国会図書館で調べないといけませんでしたが、情報を得るのが今はこんなにも楽になっているのですから。
現在のように複数社で顧問をしていると、自分の持つ知見の言語化を通じて、仕事の棚卸をするという効果も得られるのがいいですね。
本の要約サイト フライヤーのインタビューはこちらから!
IT業界の重鎮である有賀さんは、自宅が「知の図書館」になっているといいます。
- 本や雑誌の背表紙を「一覧」することで、知の体系が頭に入る
- パワーポイントはお絵かきの道具ではなく、「思考の道具」
などなど、斬新で本質を突いたアドバイスを多数いただきました。有賀さんはどんな本から知の体系を身につけ、仕事に活かしてきたのでしょうか? 続きはこちらから。
ノマドジャーナル編集部
専門家と1時間相談できるサービスOpen Researchを介して、企業の課題を手軽に解決します。
業界リサーチから経営相談、新規事業のブレストまで幅広い形の事例を情報発信していきます。