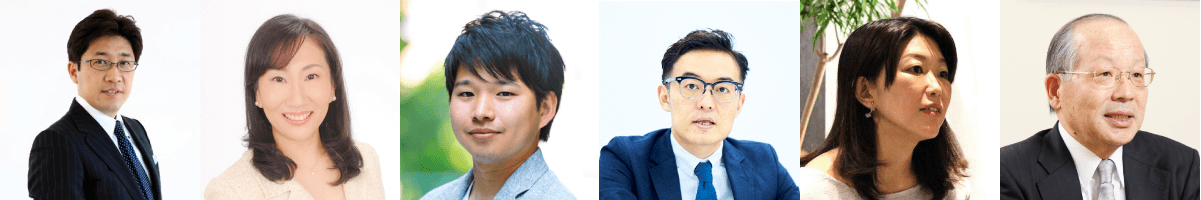前回は、「評価」と「報酬」を個別に分けて考えることで、より本質を捉えることができるという話と、評価制度についての話でした。今回はもう一つのテーマである、「報酬制度」について、解説いたします。
「人件費」と一口で言っても、その内訳は様々な使い道がある
会社が従業員に対して負担する、いわゆる「人件費」の内訳は多岐にわたります。給与・賞与といった直接的な報酬はもちろんですが、他にも退職金の引き当て、家族手当・住宅手当や通勤交通費のような手当類、社会保険料や労働保険料の会社負担分である法定福利費、慶弔金や社宅・食堂・社内レクリエーション等の福利厚生費などが具体的な範囲として挙げられます。つまり、「人件費」と一口で言っても、その内訳は様々な使い道があるのです。それを経営者はしっかりと理解した上で、会社の経営理念・戦略に基づいてどのような使途に人件費を配分するかを考えなければいけません。
経営者が考えるべき人件費の配分
経営者がまず考えるべきは、売上高のうち、どの程度の割合を人件費に費やすかです。これを測るための指標としては、「労働分配率」や「売上高人件費率」などがよく用いられます。
株主から経営を任されている経営者にしてみれば、費用の一項目である人件費を可能な限り極小化したい一方、ケチりすぎることで優秀な社員が離職したり、やる気が下がることも避けなければいけません。一方で、従業員からすれば自分の取り分が多いに越したことはありませんから、可能な限り人件費の極大化を望みます。とはいえ、過剰な人件費で会社が潰れてしまえば双方にとって元も子もありません。そこで両者の折り合いがつく状態が落としどころとなります。この「落としどころ」を決めるために、「春闘」などで会社と労働組合が交渉をしたりする訳です。
人件費の総額が決まれば、次に決めるべきはその配分です。給料・賞与・法定福利費・福利厚生費などの各項目に費用を振っていくことになります。とはいえ、現実的にはいろいろと制約条件があり、この通りにトップダウン型で決めるのは容易ではありません。その場合には、「あるべき姿」をトップダウンのアプローチで捉えつつ、現状との差分を出来る範囲で縮めていくよう努力するのが現実的な対応でしょう。
人件費を個別の社員にどのように配分するか
ここで問題になるのは、「人件費を個別の従業員にどう配分するか」です。どのようなロジックで人件費を配分して欲しいかは、個々の従業員同士でも希望が異なります(歩合を増やしてほしい人もいれば、各種手当を増やして欲しい人もいるでしょう)。これを決めるための仕組みが、広い意味での「報酬制度」となります。
企業によって業態・規模・競争環境や経営理念がそれぞれ異なる以上、「報酬制度」に唯一絶対の正解はありません。競争力最大化と経営理念の実現のためにどのような報酬制度を採るべきか、各社が独自の仕組みを真剣に考え、カスタマイズする必要があります。
ポイントは、評価制度と報酬制度の連携
ここでポイントとなるのが、評価制度と報酬制度をどのように連携させるかです。評価と報酬の相関度を高め、より「頑張った人に報い、差を付ける」報酬制度とするのか、それとも、手厚い福利厚生費・手当などで評価結果以外の部分も考慮し、評価と報酬の相関度を低くする、「平等・安定を優先した」報酬制度(年功序列型もこの一種です)とするかという問題です。
これはどちらが正しいという話ではなく、自社が求める方向性と報酬制度のあり方の整合性が取れているかどうかの問題です。
例えば、プロスポーツ選手のように個人の才能やスキルによって生産性が大きく変わるような仕事であれば、「頑張った人に報いる」報酬制度にすべきでしょう。そうしないと優秀な人ほどより「報われる」他社に流出し、そうでない人だけが残ってしまうことになります。一方で、「誰がやっても生産性が大きく変わらない」ような仕事であれば、後者の仕組みの方が従業員はより安心して働くことができます。もちろん、自社の状況を鑑みて、両方の折衷案を採るというやりかたもあり得るでしょう。
人件費配分と報酬制度は戦略的に決めるべきもの
いかがでしょうか。貴社では、このような過程を踏んで人件費配分と報酬制度について議論を深め、戦略的に意思決定をしていますか?
残念ながら、これまで各社の人事制度改革をお手伝いしてきた中では、従前の仕組みではこれらの観点が全く考慮されていないような事例も多く見受けられます。
「人件費総額のコントロール」の概念が無いために、業績に関わらず人件費が肥大化し続ける会社、年功序列的な仕組みによって従業員の働きぶり(会社に対する貢献度、成果)と報酬が連動しないために、若年層の人材流出やハイパフォーマ-のモチベーション低下といった問題が起きてしまう会社など。
そのような事態に陥らないためには、従来の「仕組み」を所与のもの・前提としないこと、そして自身の先入観、常識に囚われないことが重要です。上記のとおり、まずは「あるべき姿」を描き、現状との差分を認識していくと、今ある「仕組み」が妥当なのか疑問が出てくるはずです。過去に定められた「昇給制度」、「手当」や「福利厚生」は今でも有効なのか、それとも他により費用対効果の高い「仕組み」が無いのかをゼロベースで検討していくべきなのです。
その意味では、過去の常識であった「年功序列的な定期昇給」「賃金カーブ」などは、まず疑うべき「仕組み」となるでしょう。これらの「仕組み」の元となっているのは、「新卒で入社した従業員(男子限定)はその会社に定年まで勤め上げるべき」という前提と、その前提に基づいた「会社は従業員の生活を保証すべく、従業員のライフステージに応じて必要な給料を払わなければいけない」という「生活給」という考え方です。
一方で、最近の優秀な若者の多くは、このような従来の「日本型」の仕組みに対して懐疑的です。生活給という発想もありませんし、会社に対して長期雇用を期待していません。働いて会社に貢献した分は、「今」報いて欲しいのです。そして、この考え方は、多くの国ではむしろ普通です。
自社に最適な報酬制度を。「不利益変更」には注意。
優秀でクリエイティブな人材を獲得するためには、彼ら彼女らの望みに沿った(かつ会社の方向性にも合った)報酬制度を作る必要があります。個人の好みの差はあるでしょうが、そのような人達が概ね望むのは、貢献度と報酬の相関が高い、「頑張った人、貢献した人が報われる制度」「(長期雇用を前提としていないので)貢献に対して時間差を置かず、リアルタイムに報酬に反映される制度」ではないでしょうか。
なお、私はここで「海外の制度をそのまま取り入れるべき」と言っているではありません。何か自社にとってベストなのかよく考え、その上で自社に最適の報酬制度を作れば良いのです。
なお、従来からある報酬制度を改定し、人件費の配分を変更する場合、一部の従業員にとっては不利益なものとなる可能性が高いと思われます。そのような変更は「不利益変更」と呼ばれ、会社の意向のみで安易に変更できない場合があります。合理的な理由が無い不利益変更を実施した場合、従業員との間で重大なトラブルとなるケースもありますので、専門家のアドバイスの元で慎重に経営判断をして下さい。
新卒入社の大手ホテル業で給与・労務等人事の基礎を学び、急成長ベンチャー2社で管理部門全般(財務/経理/人事/総務)を担当。そこで感じた問題意識から慶應MBAに進む。在学中にCanadaのTop MBA, Richard Iveyに交換留学。2006年に楽天に入社し、人事評価・報酬制度の全面刷新(人材戦略室長)、買収した赤字通信子会社のPMI/事業再生(経営管理/人事部長)、二子玉川への本社移転PJ立ち上げ、CSR推進、Asia地域の人事統括(Singapore駐在)等を歴任。「ベンチャー・成長企業」「組織・人事・経営管理」をキーワードに、「成長の痛み」を未然に防ぎ、企業の健全な成長を加速させることを使命とし、2014年より独立し、複数企業の人事アドバイザリーとして活動中。
専門家と1時間相談できるサービスOpen Researchを介して、企業の課題を手軽に解決します。業界リサーチから経営相談、新規事業のブレストまで幅広い形の事例を情報発信していきます。