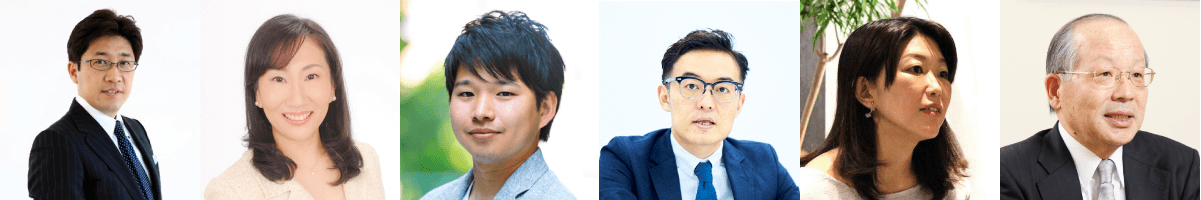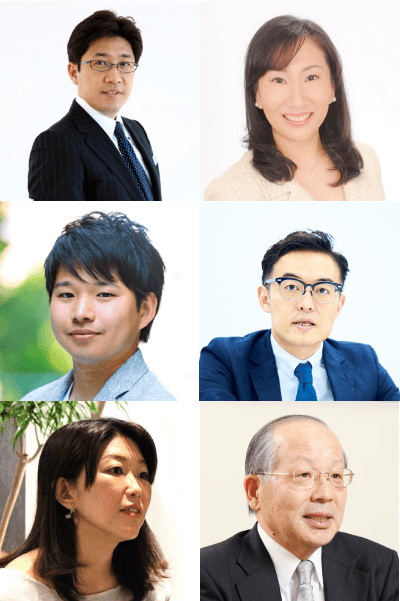瀬戸内国際芸術祭2016作品「愛のボラード」清水久和
首都圏への人口・商業施設の集中から脱却を図る「地方創生」が叫ばれる中、人気のある離島ではどのような地域づくりが行われているのだろうか?そこで、小豆島へ5年前に移住した筆者が、小豆島で活躍する企業・事業・人について取材・発信していく。
第4回は、映画「二十四の瞳」のロケ用オープンセットを改築し、お土産屋・映画ギャラリー・食事処など色々な施設を揃えた「二十四の瞳映画村」の有本裕幸専務理事にお話しを伺いました。次々と映画村の再建策を打ち出した有本さんですが、経営はどうなったのでしょうか。後編では、有本さんの経歴や想いにまで踏み込んで、お話をお聞きしました。
小豆島の色々な施設と協力しながら経営を安定させた
Q:経営状態はどのように変化していきましたか?
着任した当時は経営状況が最も危なかったのですが、現在は優良企業になっています。年間の入場者数は上下はありますが、約20万人です。平成12年は18万人くらいで、ピークの時は25万人くらいでした。小豆島の全体のバランスを見ると、現状20万人が限界かなと思っています。
集客人数は経営の上で大切ですが、それと同時に利益体質にすることがもっと大切なことです。現在、団体客が徐々に減少し、個人客への切り替えの時期に来ています。解決するべきことは沢山あるのですが、小豆島の中でも映画村は特に不便な場所にあります。そのため、アクセスの問題を最優先に考えています。
例えば、雰囲気を維持しつつアクセスを増やす意味で渡し舟を通したり、ボンネットバスを走らせたり、色々な取り組みをしながら魅力作りをしてきました。また、個人のお客様に支持されるように、マスメディアを使った試みは絶えず行っています。ただ、観光業なので、浮き沈みが大きく、うちの施設だけではどうにもならないこともあります。船でしか行けない島なので、映画村だけ良くても来てくれない。小豆島の中の色々な施設と協力して連携しながら組織を作るなど取り組んでいます。
Q:二十四の瞳映画村としては今後どのような事に力を入れていきますか?
映画村は早い時期から、他国言語のリーフレットを作成したり、施設内のトイレをすべてウォシュレットにしたりと、訪日外国人の集客に力を入れていますが、今後も海外へのPRを一層注力していきます。
最近の取り組みとして、映画「二十四の瞳」を外国の方にも理解して頂くために昭和29年作品を映画会社に依頼して、北京繁体字の字幕を入れて上映しています。ただ、「二十四の瞳」を外国人に知ってもらうのは大変なことです。日本人でも「目が24個あるお化けの映画?」というくらい知らない人がいるのに、映画を見た事のない海外の方に説明するのは難しい。だから「何の施設なの?」と聞かれた時には、映画を撮ったり、CMを撮ったり、ドラマの撮影をしたりという「小豆島にある日本映画のムービースタジオ」という切り口で紹介をしています。

全長54メートルの「シネマ・アートウォール」 写真提供/松竹株式会社
自衛隊・ホテル・現職。すべての経験が今の自分の力に
Q:様々な事に挑戦するのに、コンサルタントなど外部の力を頼らず、独自でされています。こうしたチャレンジができている背景として、これまでどのような経験をされてきたのでしょうか?
正直な所、やっている事が失敗に終わっていれば、町や役員からNOを突きつけられて解任されると思いますが、現状は成功しているので、それに関しては温かい目で見守っていただいています。新しい取り組みに関しても、支持を受けていると思っています。
もともとは全くビジネスの世界とは無縁でした。陸上自衛隊で107mm迫撃砲の火薬計算や射角度を計算するFDC(ファイヤーデレクションセンター:Fire Direction Center)という仕事をしており、米軍と合同演習を災害支援に出たりしていました。そのあと25歳から13年間、ホテルチェーンでホテルの再生や立ち上げを全国で行ってきました。自衛隊で踏みつけられても立ち上がる不屈の精神を培って、ホテルでビジネス的な事を学んで、それを映画村で実践に移してといるといった感じですね(笑)

ブックカフェ「書肆海風堂」からの眺望
Q:「二十四の瞳映画村」については一旦立て直しにも成功し、今後も様々なチャレンジをされていくと思います。翻って、小豆島全体でみた地域の課題は何でしょうか?
人口が現在約29,000人で、これからもっと減ってきます。移住者が増えてはいますが、それ以上に減少していっています。高校は統合して1箇所になってしまいますし(2017年4月に現在の土庄高校・小豆島高校が統合して小豆島中央高校となる)、大学もない。大学に行っていてそこで就職をするというスキームが取れないので、一度、島外に出ていく。そのあと何年かして戻ってくる人もいるが、戻って来ない人もいる。
戻ってくるのは歳を重ねて、「田舎がいいなあ」と感じる頃でしょう。大学があれば、4年間学んで就職するという間口ができるので、良さを活かす事ができるのにと思います。そのためには、若者がここで就業につける会社が必要ですね。この島で起業する人が増えることが最も重要なのかなあと。

「二十四の瞳」ロケセット
小豆島はSNSの時代になって恩恵を受けた場所のひとつ
Q:そうした小豆島としての、人口減少に対しての解決策はいかがお考えですか?
起業をしないと人が増えないので、若い人が新しいビジネスモデルを作るスキームを支援する形がもっと多くあるといいかな、と思います。また、小豆島の在り方としては、製造業が今まで引っ張ってきてくれていたが、時代と共に取り巻く環境に変化があり、伸びは鈍化しています。醤油や佃煮など、時代が健康志向で減塩の傾向だったり、素麺は、インスタントに取って代わられたりしています。
だから、元気を出していかないといけないのが「観光業」。小豆島にこんなものがあるという発信できるスキームを作っていかないといけない。どんなものでもいいので、協力をして、露出をしていく事を進めていく事が大事。取り組み・モノ・活動・風景・歴史・文化など今回の取材の件もそうだが、色々な切り口の小豆島の良さを外に知ってもらう為に続けていく事が大切なんです。
知ってもらうということでいうと、小豆島はまさにSNSの時代になって恩恵を受けた場所のひとつです。全国誌の記者に旅費や時間を使って来てもらわなくても、自分達で文章にしたり写真を撮ったりして個人で発信する事が容易になりました。
ツイッター、フェイスブック、インスタグラム、ブログなどで発信しているうちに、小豆島が時代の波に乗った。そこをもっと強くする意味では、海外に対して力を入れていかないといけない。現在は都市中心になっている訪日外国人も、必ず地方に来るようになります。そして、居住地をそこにする人も増えてくるでしょう。これこそが国際交流です。住んでいる側も、瀬戸内国際芸術祭で慣らしを行っていると思えばいいんです(笑)

「二十四の瞳」の撮影に使用された自転車
「二十四の瞳映画村」は、7割が行政からの出資でありながら、良い意味で行政色を全く感じさせない施設だ。その背景にあるのは、常に並行して行われている様々な挑戦である。取材でも話に上がったが、企画の持ち込み・イベント・建物の造成や改築など、大きい取り組みを年間3つは行っている。この挑戦の質と数こそが、成功のカギだろう。
その根本には、有本専務理事自身が自衛隊時代に培った不屈の精神と、ホテル立ち上げ時代に培ったビジネススキルがある。改めて、スタンスとスキルが最大化した時に、成果は付いてくるのだと認識させられた。今後の取り組みも非常に楽しみだ。
専門家:城石 果純
早稲田大学人間科学部卒業後、株式会社リクルートに入社。
入社2年目に第1子を出産した事で、時間あたり生産性の概念に興味を持つ。
第2子出産時に小豆島に移住。それ以後、時間と場所に制約を抱えながら
MVP・通期表彰などの事業表彰を獲得し続けた事で、
リクルートグループがリモートワークに取り組むきっかけを作った。
現在は、「地域と組織のサポーター」としてフリーランスで活動。小豆島在住の3児の母。
地域の良いものを掘り起こしてコーディネートする事と「ひとのチカラ」を活かす事を大切にしている。